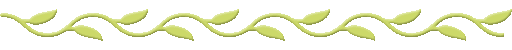
策略 女性を軍事化する国際政治
|
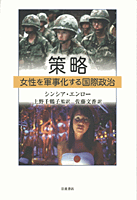 |
| 内容 第三章兵士がレイプする時 |
|
娯楽を求める兵士たち 彼女たちは戦争被害者のリストにのせられる。レイプは戦争の悪夢を呼ぴおこす。だがそれは、「戦利品としてのレイプ」というまさ に戦時の不快きわまりない混乱状態のなかで見分けがつかなくなってしまう。 したがって、特定の男牲兵士によって行われた特定のレイプを可視化しようとするとき、私たちは政 治的活動に従事することになるのである。これは意識的に行わなければならない活動だ。というのも二 つの罠が待ち受けているからである。第一に、女性たちの声に耳を傾けなければならないが、その物語 は複雑になりがちだという認識が必要である。アティナ・グロスマンは、一九四五年と一九四六年に、 主として(それだけではないが)ソビエト軍が行ったドイッ人女性に対する広範なレイプについての、つ かみにくい、しかし非常に衝撃的な歴史を暴露するというやっかいな仕事に着手した研究者である。軍 事化されたレイプ‐−残忍な戦時レイプや大量レイプでさえ−−についての「真実」を暴くことが単純 な仕事だと誤解している人々に対し、彼女は次のように警告する。「女性たちの強姦の物語は、その聞 き手や、語りの背後にある動機によって形づくられ、信じられないほど複雑に構成されていた。彼女た ちの経験は、多種多様なイメージや言説の複雑な網目のなかで秩序づけられ、意味を与えられていたのである。 第二のわなは、軍事化されたレイプを暴くことが、自動的に女性の脱軍事化につながるわけではない、ということである。男性の同胞たちに、女性のーそして彼らのーいわゆる失われた名誉のために武器を取らせようとし、彼女のつらい経験が表ざたにされるのならば、この女性は再軍事化されることになるだろう・・・ だから私たちにとって大きな課題とは、その過程で男性兵士にレイプされた女性をいっそう軍事化することなしに、彼女たちを彼女たちを目に見えるものにすることなのである。 男性兵土が「外国人」だと思っている女性に対して行うレイプ 町男性兵士が「非番中」に同じ同籍の民間人女性に対して個人的に行うレイプ 男性兵士が、以前は全員男性の部隊だったところに入ってきた女性の存在に憤慨して、あるいは、自 分とデートしようとしないとか、自分になぴかないとかで腹を立てて、同じ軍の女性兵士に対して 行うレイプ 見張り番をしている男性兵士が、軍刑務所に留置されている女性に対して行うレイプ、尋間を行う兵 士が、情報を吐かせるという明自な目的で、取り調べ中の女性に対して行うレイプ 侵略している兵士の集団が、異なる人種や民族の女性たちを故郷から追いだすために行うレイブ ある集団やある国の兵士が、主として、敵対する集団の男性を侮辱する目的で捕虜の女性に対して行 うレイブ ある民族、ある人種、ある国籍の男性が、「敵」の集団の男性をレイプすることで「たんなる女」な みに貶め、辱めるために行うレイプ 戦闘の後、部下の士気を高める褒美として、男性士官の許可により、女性に対して行うレイプ 戦時の難民キャンプの男性避難民による、あるいは、キャンプの女性避難民を守るよう任命された男性による、女性避難民に対するレイプ 売春周旋屋の男性が、兵士のための売春宿で働かせようとする女性に対して、その仕事の「準備」の ために行うレイプ 被害女性と同じ人種や国民共同体に属する民間人男性が、軍事化された雰囲気のなかで育まれ許容さ れている女性蔑視を行動に移して行う戦時のレイプ 軍事化を支待している男性が、自分たちと同じ共同体に属していると思っている女性で、軍事化に公 然と逆らっている者に対して行うレイプ リストはまだまだ続けられるが、これとて完全なものではない。 軍事化された女性と軍事化された男性との関係に徴妙なニュアンスがあるのと同様に、軍事化された レイプにもさまざまな形態がある。にもかかわらず、それらは共通するいくつかの重要な特徴を持っている。 第一に軍事化された男性強姦者はレイプする女性に対しても性的陵辱という行為に対しても、何らかの方法で「敵」「兵士であること」「勝利」「敗北」についても自分の理解をおしつける。 第二に、その結果、軍事化されたレイプは、そうでないレイプよりも、個人化・ するのがいっそう難しい。というのも、軍事化されたレイプは、社会的紛争のイメージおよぴ/または 国家安全保障や国防組織のような公的制度や武装反乱軍の機能から、その理論的根拠の多くをひきだし ているからである。 第三に、軍事化されたレイプを生きのぴた女性は、その凌辱の後、自分と強姦者と の関係、個人的な友人や親戚との関係、女性の品位という一般的な規範との関係、そしておそらく刑事 裁判制度との関係をよく考え、分、週、年といった単位で自分の対応を考えていかなければならない。 それだけでなくさらに、集合的記憶との関係、国民の運命をめぐる集合的見解との関係、そして、組織 化された暴力制度そのものとの関係もよくよく考慮しなければならない。 本章で、私は、レイプが軍事化されている特殊な条件を三つに限定して探究していく。その三つの形 態は、近年、多くのフェミニストの注意を引いているので、それらを理解することは特に重要であろう。 その三つとは、 (1)男性兵士に「十分に利用可能な」軍事化された売買春が供給されないために起こる と言われる「娯楽的レイプ」、 (2)不安に陥った国家を景気づける道具としての「国家安全保障レイプ」、 (3)明自な戦争手段としての「組織的な大量レイプ」である。 国家安全保障としてのレイプ もし私たちが売買春と関係つけられた「娯楽的」レイプや戦時レイプにばかり関心を向けるなら「国家安全保障」に対する脅威と考えられるもので頭がいっぱいの政権の下で、女性たちを軍事化するためにどのようにレイプが利用されてきたのか見落としてしまう危険性がある。 国家安全保障というフィルターを通して国内の政治的対抗勢力を見ている全ての政権が、必ずレイプを行なうわけではない。 イギリスのフェミニスト研究者サラ・ベントンはいかなる内紛でのレイプ利用にそれぞれ個別の問いを立てるようーつまりレイプを自明のものと考えてしまわないようー私たちに警告している。 (1916年のイースター蜂起後のアイルランドの武力紛争を調査した彼女は)イギリスの治安部隊が行なった残酷な手段を用いたことのたくさんの証拠を発見した・・・1920年代の紛争がジェンダー化されていなかっらとも結論づけはしない。むしろ彼女はさらに踏込んで、イギリス軍によって広範なレイプが行なわれているというアイルランド民衆の思いこみがナショナリズム運動にアイルランド女性を動員するためにいかに利用されたか、そして同時にアイルランド女性は無力でありアイルランド・ナショナリストの男性藤氏の「兄弟愛」の庇護を要するのだというイメージを保持するのに、いかに利用されたかを検証した。 国家安全保障の名のもとで、軍事化されたレイプがとりわけ生じそうな条件とは、 1.その政権が「国家安全保障」にかまけている時、 2.民間人の大多数が、安全保障とは軍事的な問題としてもっともよく理解できるものだと信じてい る時、 3.国家安全保障の政策立案が、主として男性化された政策エリートにまかされている時、 4.警察と軍隊という安全保障機構が男性に支配されている時、 5.名誉、忠誠、反逆の定義が、警察や軍隊の制度的文化にもとづいている時、 6.それらの支配的な制度的文化に、性差別的な女性蔑視がある時、 7.安全保障上の脅威であると見なす男性が、父、恋人、夫としての立場においてもっとも脆いと安 全保障当局によって見なされている時、 そして、童要なのは、 8.地元の一部の女性たちが、その政権の政策に対する組織化された反対勢力として、公的に目立つ ようになりはじめている時、 これら八つの条件のうち最初の七つが進行するにまかされれば、たとえその国が戦争状態になくても、 軍事化されたレイプが起こりうる。そして、一九七○年代後半には、フィリピンやチリのようにそれ以 外には共通点のない国々で、八つのすべての条件が成立したのである。 フィリピン チリ 「戦利品としてのレイプ」 戦争、レイプ、フェミニズム、ナショナリズム 1994ルワンダ 1991〜1995ユーゴスラビア 野獣、少年、紳士 |
|
|
結論ー決定、決定、決定 | |
(ヴァージニア・ウルフ「三ギニー」) スペイン内戦(この戦争でウルフは最愛の甥を亡くした)の恐怖について語り、近々また新たに世界戦争が始まるのではないかと懸念していた時期であったにもかかわらず、自分が暴こうと心に決めていたことが、拍手喝 采で受けいれられることはないだろうと予測していたのである。というのも、たんねんな調査の後で (その注釈はエッセイ本文と同じく驚愕に値する読み物になっている)、ウルフは、法律、大学、市民的 奉仕、中産階級的洗練といった、多くの英国人が自分たちの民主的文明の核心であると誇らしげに考え ている制度や文化的性向そのもののなかに、戦争の根源がくみこまれているという結論にいたったから である。その各々のなかに、ヒエラルヒー、競争、男らしさの特権化という軍事主義の三位一体を促進 ざせるさまざまな想定やしきたりが織りこまれていることに、彼女は気づいた。 『三ギニー』はいまだに、読むたぴ新しい発見をもたらしてくれる。ウルフは、この本のなかで、男 性化された文化が政府の公務のなかで継承ざれていることを指摘しただけではなかった。彼女は、もし も若い女性たちが、ヒエラルヒーや競争という男性化された職業規範を無批判にとりいれるならば、女 子大を支持したり、法律や医療の分野で女性を抜擢しようとすることでさえ、こうした女性たちを軍事 主義の共犯者にしたてあげることになりうるのだと、読者に警告したのである。 本書の裏づけとなった研究は、ウルフの二重のメッセージの意義を証明している。 (1)軍事化はわかりきった場所においてのみ起こるのではなく、爆弾や迷彩服から遠く離れた人々、 モノ、概念の、意味や用法を変えることもできるということ。 (2)軍事化は男らしさを特権化するが、女らしさと男らしさ双方の意味を操作することによってそうするのだということ さらに、本書におさめられた証拠は軍事化がただたんに偶然起こるわけではないことを示唆している。 それは決定を、多くの意思決定を、民間人と軍人双方による意思決定を必要とする。そして、意識的な 決定を行うとはいえ、通常、軍事化を進める意思決定者は、論理と利権のたんなるマシンではない。彼 らは矛盾と葛藤に苛まれ、しばしばもくろみどおりの結果を得ることができないでいる。本書の読者は いたるところで−−おそらく米軍の傘論争のところで−−苦笑したり、時にはおもしろがりさえするだ ろうが、そうした反応は、軍事化が矛盾をともなうプロセスでありうる証拠として受けとることができ るだろう。 ウルフの根源的な分析は、彼女に根源的な戦略をとらせることとなった。女性は、軍事化を促進する あらゆるブロセスから十分に距離をとるべきである、と。しかし、本書では、国内外の軍事化推進者と 闘うために、フェミニストの女性たちが、さまざまな戦略を選ぴとっていること、そして、そうした闘 いが必然的にともなう複雑なリスクをひきうけていることを示してきた。 起こったばかりの第一次仕界大戦の荒廃やスペイン内戦の前兆を敏感に感じとり、クリミア戦争やボ ーア戦争の記憶を持っていたウルフの同時代人たちは、ものごとには日常的に軍事化されやすいものが あるということによく気づいていた。六○年後、ウルフの子孫である私たちは、次のものがなぜ、どの ように、そしてどんな結果をともなって軍事化されるのかを正確に理解しようと、いまなお努力してい る。 (軍事化されうるもののリスト) ナショナリズム 男らしさ 人種差別 母性 英雄的行為 女性参政権運動 売買春 政府予算 よい仕事がほしいという女性たちの願い 秘密主義 性病 他方、どれほどの範囲のことがらが軍事化されうるのか、その詳細が明らかになってきたのはごく最 近のことであり、私たちは今日なお、次のものが軍事化されることをほとんど理解していない。 洗濯物 傘 ガードル ドメスティック・バイレンスの防止 女らしい尊厳 マスカラ 民主主義 科学的研究 結婚 フアツシヨン 安全保障 一級市民権 故郷の誇り 同性愛嫌悪 反同性愛嫌悪 そして、新世紀の夜明けに、軍事化されうるもののリストはさらに広がっている。 社会的地位の上昇 解放運動 レイプ人道支援 平和維持 エイズとエイズ予防 文民裁判官 子どものおもちや産業 映画のシナリオライター 選挙運動 女らしさ スニーカー 軍事化とは、自動的に起こるものではない。ここにあげたどの項目も必然的に軍事化されるわけでは ないだろう。軍事化とは、何かが徐々に、制度としての軍隊や軍事主義的基準に統制されたり依拠し たり、そこからその価値をひきだしたりするようになっていくプロセスである。 軍事化されたものは脱軍事化されうるし、脱軍事化ざれたものは再軍事化されうる。 それゆえ、一足のスニーカーは、(中国 やインドネシアやヴィエトナムで)それをつくっている女性たちの賃金が低くおさえられているかぎり、 軍事化されていると言える。なぜなら、大手のブランド企業やその請負工場は、彼女たちの監督者とし て元軍人を雇ったり、労働組合づくりをおさえるために軍事化された地元の保安隊を招集したり、「国 家安全保障」のためには女性労働者の独立組織があってはならないとする政府と手を組んだりするのだから。 スニーカー会社がこうした管理技術を止めるならば、そのブランド名のついたスニーカーはその程度に応じて脱軍事化されるだろう。 さらにいくつかの例をあげよう。国家の安全保障や家庭内の安全を求めるだけでなく、住宅や医療を 求めて兵士と結婚した女性が、夫に依存する程度に応じて、その結婚は軍事化される。兵士(や退役兵) と結婚した女性が、自分は、自国の政治的出来事に対して自分自身の権利を持った自律した公的行為者 だと考えるなら、あるいは、夫の上官の評価を気にせずに、自らのキャリアとして追求しうるような有 給の職業についているならば、その結婚を脱軍事化していることになる。また、国際人道支援を例にと ろう。国際赤十宇やユニセフのような機関で働いているスタッフの話では、戦争行為によって難民とな ってしまった人々に確実に救援物資を届けるためには、今日、ますますひんぱんに、NAT0軍へ護衛 の要請をしたり、地元の指揮官と難しい取引をしなければならなくなっているという。こうしたスタッ フは、自分たちの支援活動が、おそらくその活動の組織文化さえもが、軍事化されてきているのではな いかと懸念している。彼ら/彼女らは脱軍事化を犠牲にし、したがって自分たちの職業の本来の姿も、 武力紛争による犠牲者たちの信用をも、結果的には犠牲にしてしまっている、と感じている。 しだいに進行する軍事化のプロセスは、通常、決定‐−特定の人々による意思決定−−によって前進 する。今まで見てきたように、こうした意思決定者たちは必ずしも軍のトップである将軍たちとはかぎ らない。そのなかには地方の軍事基地司令宮をしている大佐もいれば、従軍牧師や医者や心理学者や新 兵募集係もいる。こうした意思決定者の選択によって、軍人の妻や女性兵士のスカートの裾のラインや、 国際機関の救援活動が軍事化されるかどうかが決まるのだが、なかには、今までに一度もカーキ色の軍服を着たこともなければ誰にも銃を向けたことのないような人々もいる。 服を着たこともなければ、誰にも銃を向けたこともないような人々もいる。現在およぴ過去の軍事化の 加作用を徹底的に調べれば、これら軍人以外の意思決定者のなかには、市長、ファッションデザイナー、 固会議員、社会科学者、映画製作者、おもちや製造業者、ジャーナリスト、国連職員、民族集団のリー ダー、広告業界の役員が含まれていることが明らかになる。 軍事政権と対立している運動のリーダーでさえ、男らしさを特権化し、一部の男性と大半の女性を周 縁北するようなやり方でその運動を軍事化する決定を下す場合には、軍事化されうる。 独裁政権が、広 まりゆく人民の抵抗を打ち砕くために機動隊を召集する時、反対派のリーダーは、豪胆で、筋骨隆々の、 男らしさを誇る男たちを最前線におくという軍事化された対応で対決することを選択してはいないか? そうだとしたら、女たちはどこにいるのか? 通常、女たちは後方ヘ、前線の男たちの支援者や崇拝者という女性化された役割のなかへと、押しやられる。体制側が機動隊を石集している時に、民主化運動の女性たちが、自分たちが多くのエネルギーを注いでいる運動を軍事化する決定を見抜くことは難しい だろう。 それにもかかわらず、こうした条件下で、民主化運動の反軍事主義が軍事化されるというあり そうな結果を重視し、より軍事化されない抵抗の形態、女性の声に対して開かれた空間を保つような革 新的な抵抗の形態を考えようとしている者もいる。ベオグラードの「ウィメン・イン・ブラック」が笛 を配り、沖縄の女性活動家たちが「行進する」よりむしろ「歩く」ほうを選んだことにも、こうした抵 抗の重要な特徴がある。 しかしながら、民主化運動に加わっている多くの女性たちも、熱狂的な抵抗運 動の最中に下された以前の決定のなかに、長期にわたる男性化の含意があったことにはなかなか気づか い。 軍事化は単純なプロセスではないし、容易なプロセスでもない。軍事化を推進し、維持するには数多くの決定を要する。 女性の軍事化にとって不可欠な決定のなかには、次のような不作為の意思決定もあ る。ストリッパーを部隊のパーティの中心に持ってくる若い士宮たちをおさえないという上級士官の決 定、部下の男性が同僚の女性に行っているセクシュアル・ハラスメントを見て見ぬふりをするという上 級士官の決定、政府軍の売買春政策をおおっぴらに考慮すべきトピックとはしないという文民政治家の 決定。軍事化を監視するのがしばしばとても難しい理由のひとつは、それが、作為と不作為、双方の意 思決定の組み合わせによってひきおこされるからである。 フェミニストとして思考し行動している女性たちのおかげで、いかなる軍事化プロセスも、女らしさ に関する特定の考えと女性の労働や感情に依存していることが、暴きだされてきた。 戦争の原因を論じ ているおおかたの月並みな評論家たちは、女らしさと女性をさまつな間題として扱っている。戦争とい うメインイベントは男らしさの遂行であり、エリート男性によってなされる会的な選択だと考えられて いるからである。こうした観察者たちは、分析範囲を狭めることで、政府と政治運動双方のリーダーに よってなされる計略の質と量を過小評価していることになる。つまり、軍事化をスムーズに進められる ような役割へと女性たちを巧みに操っていく決定を、たいていは無視することによって、こうした従来 型の(非フェミニストの)政治評論家は、政治権力の作用を過小評価する。 彼らは、アメリカやロシアや 韓国の政策立案者が、軍隊の売買春政策を一度もつくったことがないかのように書く。どうやって、あれ ほど多くの男性が、故郷の同胞である女性をレイブするように仕向けられたのかを考えてみようともせず ルワンダ大虐殺を分析する。 兵士と結婚した女性たちはみな「生まれつき」従順な妻であるかのように、軍隊内の情事を論評する。セルビアのミロシェビッチ大統領が、母性の政治学について考えもせずに、コソボ自治州への軍事作戦に着手できたかのように語る。 こうした傾向に抗して、フェミニストたちは政治的観察の範囲を広げるべく、さらに好奇心をはたら かせてきた。 彼女たちは「女はどこにいるのか?」と間うてきた。 そして、この基本的問いに対し、さ らなる三つの問い−−「どんな女がそこにいるのか?」「この女たちはどうやってそこにたどりついた のか?」「その女たちは、そこにいることをどう思っているのか?」をつけ加えてきた。 「そこ」はさまざまである。「そこ」はテルアビブの交差点における沈黙の抗議かもしれない。軍事基地のすぐ外にあるディスコかもしれない。あるいは、軍の病院のベッドサイドかもしれない。つまり、フェミニスト的好奇心をはたらかせれば、分析者は次のような問いへと導かれる。いかなる社会であれ、制度としての軍隊と公的活動としての車務に優先的な価値を与えるべく、政府の公的優先順位づけが行われる時、特定の女性たちに特定のやり方で政府を支持させるにはどんな策略がとられるのだろうか?こうしてフェミニストの分析者たちは、政府や政治指導者らが多くの時間と資源をつぎこんで、思実な妻、愛国的な母、現代的な女性、プロの看護婦、健康な売春婦、恥じいるレイプ犠牲者、物わかりのよいガールフレンドであるとはどういうことかを形づくってきたことを発見した。軍事化推進者は兵士の大半が男性であることを望むかもしれない。戦争遂行の政策づくりには男性しか信用しないかもしれない。軍事費の議会における支持を確かなものにするカギを握っているのは、男牲政党員だと信じているかもしれない。 こうしたすべての要素にもかかわらず、フェミニストたらの発見によれば、軍事化推進者たちが女性を気にかけていないということにはならない。 軍事化推進者たちは、もし女性を効果的に統制することができなければ、軍事化という事業への男性 の参加は保証されないともっぱら信じていると見える。だからこそ、女性、およぴ女らしい尊厳、女ら しい義務、女らしいセクシュアリティ、女らしい技能に関する観念そのものを、政策と説得の対象にし なければならない、と彼らは考えている。女性に間する決定とは、紛争のまっただなかにおいてのみ下されるべきものなのではなく、予想される紛争に先立つ何年も前から、そして、紛争後何年にもわたっ て下されなければならない。この発見のおかげで、軍事化の男性化された特権が社会に対して持ってい る影響について意識的なフェミニストたちは、表面上、平時あるいは「戦後」のように見える時でさえ、 女牲と女らしさの軍事化を監視し、それに対応する必要があることを悟るようになった。 過去二○年のあいだに、多くの社会におけるフェミニストの思想家や活動家たちは、女性のあいだに 存在する差異に対して、かつてより明確に注意を払うようになった。インドのフェミニストは、インド におけるイスラム教徒とヒンドウー教徒の女性たちの価値観や環境の差異を理解することに、知的エネルギーを注いできた。メキシコのメスティソ系都市中産階級のフェミニストは、田舎の先住民女性や都 会の工場労働者の女性たちが、自分たちには思いもつかないような日々の要求に対処している様子を描 きだそうとしてきた。北アイルランドのカトリックとプロテスタントの女性たちは、新たな市民社会を うちたてるのに貢献できるよう、共同体をまたがる効果的な集団づくりをめざして、自分たちの国の問題について活発な分析を発展させてきた。 どの例においても、女性間の差異を維持することによって、 女性の軍事化が容認されてきたのであり、したがって、たとえ軍事化された暴力の、もっとも目につきやすい犯人が男性であっても、女性間の差異の継続がその暴力をあおる決定的な要因となっていた。このような分析的な理解がフェミニストたちをつき動かしてきたのである。 (フェミスト運動と女性間の差異) フェミニストが女性のあいだに存在する差異に気づいたのは、まったくはじめてというわけではない。 一八八○年代のイギリス、ドイッ、アメリカにおける女性の権利論者、あるいは一九二○年代のヴィエ トナム、インド、エジプト、日本、プラジルにおける女性の権利論者を、「シスターフッド」が自動的 に存在するものと想像し女性を均質の集団と考えた、ナイーヴな世間知らずとして描くのは誤りである。 こうした初期の活動家たちは、異なる民族や人種に属する女性間の差異、不平等な社会階級に属する女 性間の差異、違うだけでなくしばしば敵対する宗教的伝統を持つ女性間の差異、対抗する政治的イデオ ロギーを支持する女性問の差異、田舎の村に住む女性と都会に住む女性間の差異について記述し、論じ てきた。 しかしながら、差異に意識的であったことは、初期における女性の権利論者たちが、こうした 違いによって(しばしば、男性士官や政党指導者があおることで)生じる差異と不信を克服するための理 論的かつ戦略的な選択をつねに行ってきたということを意味するわけではなかった。女性活動家たちは 往々にして十分に深くは探究しなかったのだ。彼女たちは時に、自らの認識が持っている個人的で戦略 的な意味から逃避した。そして、女性活動家たちのこの失敗、つまり、領域横断的な同盟をつくりだし、 女性を分断している障壁を低めることに失敗したことで、軍事化というプロセスはたぴたぴスムーズに 進められることになったのである。 新世紀の幕間けに、軍事化は、互いに知らず、関わらず、敵対的で すらある、異なる社会的・経済的・イデオロギー的・文化的位置におかれた女性たちに頼りつづけてい いる。 現代のフェミニストのなかには、過去に分裂を経験することによって、こうした差異を理解し,差異が誘発する敵意を減じることに、より多くの知的で組織的なエネルギーを費やすことになった人々もいる。 女性たちは軍事化推進のために異なる方法で、異なる機能を果たすために軍事化ざれている。たとえ ば、看護婦として軍事化された女性は、ふつう、売春婦として軍事化された女性とは、経済的・文化的 背景、時には民族的背景すらもまったく異なっており、一般に、あまり尊敬に値しないと考えられてい る女性とは、はっきり区別される利害関係を発展させている。下士官兵の妻として軍事化された女性は、 通常、上級士官の妻として軍事化された女性とは、民族的にも経済的にも異なる出自の持ち主である。 難民として軍事化された女性は、人道支援機関で働く、目につきにくいが軍事化されている女性とはま ったく違う人生を生きる者として自らを認識しているかもしれない。さらに、このように異なる仕方で 軍事化されるという経験そのものが、それ以前にとっくにイデオロギーや階級や民族によって互いに分 断されている女性たちのあいだにある障壁を、いっそう高めるのに役立つこともある。 しかしながら、女性どうしの分断に注目することは、「女性」などいない、すなわち、女性とは綿菓 子のように空虚な分析カテゴリーなのだと主張することと同じではない。 たしかに、「女性」という神話的な一枚岩の生き物は存在しない。しかし、それは、「女性」などいないという先の言明とはまった く別の間題である。 女性の自己認識や女性の労働が軍事化に貢献しうるような位置へと、彼女たちを巧 みに操っていこうとする大半の意思決定者は、次の二つの前提に同時に従って行動してきた。 (1)意思決定者たちは、「女性」という集団があり、たとえ互いにどんなに異なっていようとも、共通巧 の「女性性」を有していると信じてきた。 (2)意思決定者たちは、女性は多様であり、したがって、政策づくりにあたってはそれぞれの社会文 化的な位置に応じてとりあつかわれるべきであると信じてきた。 その結果、実質的にはすべての社会の女性たちが、たとえ民族的・宗教的アイデンティティ、地理的居 住地、歴史的世代、経済的階級を等しくしていたとしても、男性たちとはまったく異なった軍事化を経 験してきたのである。 一九九○年代のラパスで貧しい都市近郊に暮らしていた先住民のボリビア人女性 には、自分の夫と共通点がたくさんあるが、大学に行き専門職につくような資源を有するボリビア人女 性とのあいだにはほとんど共通点がない。それにもかかわらず、自らの国の−−そして自らの政権の −−安全保障は、若い男性を、特に貧しい地域の男牲を国軍へと徴兵することで成り立っていると信じ ているボリビア政府当局が、先住民女性と彼女の夫に同じやり方でアプローチすることはないだろう。 政府は夫と妻の両方に、それぞれに異なった役割を求めている。彼女は女であり、女として第一義的な 役割を母として想定されているのだから、兵役をおえた若い男性を、男らしく、成熟した、結婚可能な 若者と見なしつづけることを奨励されるにちがいない。同様に、軍事主義的武装勢力によって難民にさ れてしまった女性と、軍務につく男性と結婚することで自らの頭上にいくらか安全な屋根を手にした女 性とでは、ほとんど共通点がないように見える。それにもかかわらず、軍事化推進者は、どちらのグル ープの女性にも、女として性的に利用可能であること−‐難民キャンブの見張り番の男に対してであれ、 休暇で自宅にいる男性兵士に対してであれ−−を求める。この二組の女性たちには、腰をおろして意見 交換したりするチャンスはけっしてないだろう。たとえ、いっしょに同じ部屋にいたとしても、互いに 画そうとはしないかもしれない。だが、もしも、彼女たちがそのような交流をする方法を見つけたら、 に気づくだろう。 たんに女性であるというだけですべての女性が連帯して当然、と考えないことは、信頼にたる因果分 析を行い、効果的な戦略をつくりだすには決定的に重要である。しかしながら、このような結論にいた ったからといって、「女性」が軍事化の原因と結果を理解するうえで役に立つ、正真正銘の政治的カテ ゴリーなのだという信念に対する確信をすべて捨てろと要求しているわけではない。 軍事化を経験してきた女性たちのあいだに領域横断的な連携をつくりだすことは、けっして単純なこ とではないが、もっともうまくいった事例は、軍事化の経験によって犠牲にされてきたと信じる女性た ちのあいだの連携、ならぴに、自らの政治的活動を軍事化の犠牲者としての女性を支援することに捧げ てきたフェミニストたちのあいだの連携であった。こうして、戦時の組織的なレイプを国際的に認識さ せ、「人道に対する罪」をハーグやアルーシャの国際法廷で起訴すべく、国家横断的、階級横断的、民 族横断的な運動が展蘭されてきたのである。かくして、今日のグローバルな政治経済において異なった 位置にあるにもかかわらず、日本、韓国、台湾、フィリピンのフェミニストたちもまた、かつての日本 の体制が有していた「慰安婦」制度を生きのぴた高齢の女性たちに対して公的な賠償責任をとらドよう と、日本政府に圧力をかけるべく、こわれやすくはあるが機動的な政治的連携をつくりあげてきた。 しかし、軍事化を経験している多くの女牲たちが、自分自身をこのプロセスの犠牲者として見るとは かぎらない。依然、女性として政治的に周縁化されているにもかかわらず−−そして、おそらくは、女 性として政治的に周縁化されているにもかかわらずー−これらの女性たちは軍事化を、もしそれがなければも てなかっただろう諸々の機会−−兵士である夫の昇進を通じて社会的地位を上昇させる機会、軍に入隊 することで結婚を遅らせ「女向きでない」分野で訓練を受ける機会、戦時にふだんの家事を能率的に行 うことで愛国者としての信頼を得る機会、軍事化しつつあるナショナリズム運動において「国民の母」 の代表として会的に発言することで政治的役割を演じる機会−−を提供してくれるものとして認識して いる。 もし、軍事化があらゆる状況のあらゆる女性にとって抑圧的なものであるならば、これほど影響力の ある政治的プロセスとはならないだろう。軍事化の意思決定者の策略を見きわめるのが難しく、その根 本的に家父長制的な帰結を見破るのが困難であったのは、まさに、一定の時期の一定の女性たちに対し て、軍事化が利益をもたらすからなのだ。さらに、いかなる社会においても、女らしさを軍事化するこ とで利益を得ている女性たちがいることが、軍事化を遅らせたり後退させたりする広範なフェミニスト 同盟をつくりあげるのを難しくしている。兵器工場の労働者として、軍隊看護婦として、候補生部隊の 女子生徒として、こうした少女を娘に持って鼻の高い母として、軍隊内のセクシュアル・ハラスメント を深刻に受けとめるよう軍隊に圧力をかける政治的ロビイストとして、軍隊の階級を昇っていく男性と 結婚した女性として、新たな国軍に居場所を見つけたいと思っている元反政府ゲリラとして、これらの 女性たちは、むしろ、よりいっそう軍事化を自分自身の間題の解決策と見なすかもしれない。こうし た女性たちの目からジェンダー化された軍事化政策を眺めると、男性の意思決定者は女性たちを軍事化 された役割に完全に統合したがってはいないことに気づく。彼女たちの分析によれば、家父長制は軍事 化の伴侶なのではない、むしろ、家父長制は女性や少女たちを完全に軍事化するうえでの障害となっていると見えるだろう。 したがって、一九九五年の米海兵隊員らによる少女レイプ事件の後、地元の怒りを結集した沖縄のフ ェミニストたちと、性差別主義的態度を持った海軍大将を非難することでメディアの関心を最大限にひ きつけた、ワシントンを拠点とするアメリカのフェミニストたちとが、政治的平行線をたどっているよ うに見えたのも、驚くことではない。結果として、彼女たちが同盟をつくりだすことはけっしてなかっ た。 それぞれの女性グループは、男性化されたふるまいを批判することにまっしぐらに突き進むことに よって、政治的リスクを負っていた。どちらのグループの女性たちも、自らをフェミニストと定義して いた。どちらのグループも国家と対決していた。だが、彼女たちは、軍事化と家父長制の関係に対して、 完全にあいいれないわけではないにしても、きわめて異なったアプローチをとっていた。 沖縄のフェミ ニストたちは、日米双方の軍事主義を解体することが、女性にとっての身体的安全と政治的エイジェン シーを保証する唯一の道だとする理論にもとづいて行動していた。 対照的に、議会を通じて行動し、国 防総省に圧力をかけていたアメリカのフェミニストたちは、沖縄から軍事基地を撤退させることはフェ ミニストの優先課題ではないと信じていた。 彼女たちの目的は、米軍司令官の買春奨励を暴き、米軍内 の性差別に挑戦することだった。そうすることで、アメリカの軍人としてキャリア形成を望む女性が、 女牲蔑視のない雰囲気のなかで任務を遂行できるようにと考えてのことだった。 軍事化によって抑圧されている女性たちのために働く女性と、軍事化を通じてより大きな機会を求め ている女性たちのために働く女性が、互いに何の共通点もないと考えること、あるいはもっと悪くすれば、互いを政治的な敵対者であると想定する方向に気持ちが傾くかもしれない。だが、こうした思いこ みは、ジェンダー化された軍事化の全貌を検証されないままにしてしまうだろう。 軍事化というプロセ スは、女性を男性とは区別して扱う。このプロセスは、一部の女性たちを包摂することによって、彼女 たちがいくらかの新たな機会を得る場合でざえ、実質的にはつねに、男らしさを特権化する。軍事化は また、さまざまに異なる状況にある女性たちが背後にあるダイナミクスに気づかないことに依存するプ ロセスでもある。 分析することと、その分析で何をするのかは、別のことである。軍事化された女性た ちのなかに、軍事化された他の女性たちとの政治的同盟をつくることを避ける者がいるだろうから、と いうただそれだけの理由で、軍事化を進める意思決定者のジェンダー化された策略という完全装備を解 き明かさずにいるのであれば、それは結局のところ知的損失となるだろう。 フェミニストとして、軍事化に立ち向かってきた女性たちは、その努力がリスクを−−たんに嘲笑さ れたり逮捕されたりといったリスクだけでなく、結果として家父長制を再ぴ活気づけることになるかも しれないというリスクを−−ともなっていることを発見した。これまでの一連の研究から明らかになっ たことがらのうち、以下にそのなかから五つの難問を掲げてみた。 (1)軍事化された制度(軍隊、防衛産業、国家安全保障機関、立法府の外交委員会、国連平和維持軍) 内の性差別的実践に抗してロビー活動を行っているフェミニストは、どのようにして自らの目的を 達成することができるのか? ただし軍事化された制度に対して、政治文化における優先的価値を与えるというリスクをおかす ことなしに。 (2)(通常、公的な出来事に対して意見を述べることのできる場所がないと感じている)女性たちを 政治的に活動的にするために、母としての意識に依拠しているフェミニストは、どのようにしてそうすることができるのか? ただし、女性を母へと回収することなく、かつ、 母性を、女性たちが政治的行為を行うことのできる唯一の正統な場とすることなく。 (3)フェミニストは、どのようにして、戦争におけるレイプの利用を明るみに出し、兵士にレイプさ れた女性たちへの支援を動員することができるのか? ただし、レイプ被害者の女性を「国民的屈辱」のシンボルに変えたり、レイプのニュースが男性化 された復讐心をあおったりすることを許さずに。 (4)フェミニストは、どのようにして、軍隊という制度が性差別と同性愛嫌悪に文化的に依拠してい ることを示すべく、軍隊を保護している覆いを剥ぎとることができるのか? ただし、女性の軍隊参加や軍隊内での昇進を、すべての女性が「一級市民権」に向かうステップと 解釈させずに。 (5)フェミニストは、どのようにして、フェミニスト意識を持ったもっと多くの女性たちが、国家や 国際機間で政策ポストに任命されるようにすることができるのか? ただし、軍事化に対するジェンダーに敏感な批判的アプローチが、参入の代償になるという犠牲な しに。 フェミニストと軍事化との関係を複雑にしているのは、またしても、軍事化プロセスの広がり、およ び、大半の男性だけでなく多くの女性たちもあずかる軍事化プロセスから生じる利益なのである。 今日では、その複雑さは、進行しつつある軍事化プロセスの国際化によって増大している。軍事訓練 教官の外国派遣、海外基地の維持、NATOの拡大、軍事政権が支配する国々ヘの企業の資本投資、過 去の戦争に対する賠償交渉、国連の平和維持任務の遂行、内戦による難民への資金供与、グローバル化 したメディアを通じた兵士のイメージ構築、国際的な武器の売買、常設の戦犯法廷づくりの外交交渉 −−こうした決定がいずれの形態をとるにせよ、国際的な政治プロセスは特定の決定によって動かされ ている。それぞれの国際的な政治プロセスにおいて、これらの決定は、たんに、女性にとって男性とは 違う意味をもつというだけではない。 これらの決定は、それぞれ違うかたちをとったとしても、「女ら しさ」の特定の意味の構築に依存するだろう。女らしさの概念と、女性という行為者は、たんに国内政 治の有益な分析の主題として適切だというばかりではない。女らしさの概念と、女性という行為者は、 私たちが国際政治のプロセスを理解しようとする際に、知的好寄心をもって分析対象とされる必要があ る。国家間および国家内部で進行中の軍事化の途上につまずきの石があるとすれば、それはフェミニス ト的好奇心というかたちをとるであろう。 | |
|
訳者あとがき | |
本書の最後に「軍事化の途上につまずきの石があるとすれば、それはフェミニスト的好寄心というか たちをとるであろう」232頁)と記されたその「フェミニス ト的好奇心」を前面にうちだしたタイトルで、二○○四年には、これまでのエンローの仕事をおさめた論集も出版されている。本書をきっかけに、 エンローからの呼ぴかけに応えて「フェミニス ト的好奇心」をはたらかせ、(私自身をも含めた)日本の読者が次のようなさまざまな課題にとりくまれることを心から願っている。 ・バブル期に女性自衛官を飛躍的に増大させた自衛隊の政策と市場経済の家父長制的性格との関連性 を「フェミニス ト的好奇心」で眺めてみたら? ・二一世紀に台頭してきたジェンダー(フリー)・バッシングに従事する人々の関心を、国家安全保障を支える男らしさ/女らしさという観点から「フェミニス ト的好奇心」で眺めてみたら? ・防衛庁の省への「昇格」を目前に、「防衛国際平和省」や「防衛国際貢献省」といったネーミング に知恵をしぼる与党議員の策略と、これを「戦闘服にリボンをつけて「自衛隊は変わった」という のでは、世界の笑いものだ」(朝日新聞2005.12.24朝刊)と記した新聞記者の男らしざを「フェミニス ト的好奇心」で眺めてみたら? ・9・11後のアメリカで、「ビンラディンの姪」が、男性誌にモデルとしてきわどいポーズで登場したことを、センセーショナルにとりあげるメディアの男らしさを「フェミニス ト的好奇心」で眺め てみたら? 二○○三年に本書の翻訳のお話をいただいて、はや三年、ようやく刊行の運ぴとなり本当にほっとし ている。本書をつくりあげる過程で、エンローの次の文章が私のなかで何度こだましたことだろう。 本はたまたま「できる」のではない。それはさまざまな選択や決断をする人々の手によつてつくり だされ、売られる。編集者から書店の店員にいたるまで、出版業界のあらゆるレベルで選択・決断 をするフェミニストたちのおかげで、女性たちの政治的生活に関する経験と思考をまともにとりあ げる本が出版され、私たち残りの者がその本を読むことができるのである(17貢)。 |
 トップページへもどる
トップページへもどる