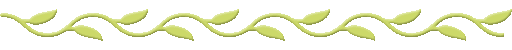
Sale of the Century
第二のロシア革命の内幕
|
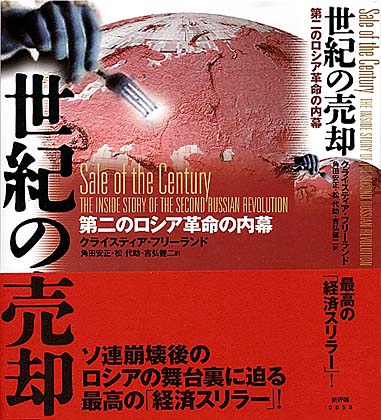 |
| 内容 | |
| (使命と現実) 1991年「資本主義のボルシェビキ=若手改革派のスター、血統書付きのボルシェビキであるガイダール、鉄の将軍チュバイスの台頭からストーリーは始ま る。 崩壊するロシア国家によって国有財産は「インカ帝国を略奪したスペイン人なみに、それを大急ぎで海外の聖域に移転した。1992年から2000年の間、 1000億ドルないし1500億ドルの資本がロシアから流出した。「ザル経済」と評される大混乱のなかでセール・ワゴンに群がった人々によるつかみあいが 始った。この私有化で、税収、教育、医療、年金などロシア社会のインフラは崩壊する。内陸中央部に多数存在する工場・鉱山地帯での混乱。 「マルクスから共産主義について教えられたことはすべて嘘だった。しかし、資本主義について教えられたことは何から何まで本当だった」 2000年、ところで気が付いてみると、彼ら(若手改革派)には政治基盤がなかったのである。 国有財産を個人に移転することには驚くほど成功したが、しかし私有化された企業の効率と収益性の改善という真に重要な尺度では、彼らの実績にはムラが多 かった。 「腐敗に目をつぶって民主化を優先する」民主化と腐敗の組み合わせは偶然の取り合わせではなく、完全に意識的な実利優先の選択であった。 (プーチンの登場) 私にとってもっとも現実的なのは、ロシアが穏健タイプの権威主義体制へ転落するというシナリオである。アパラチキ(ソ連時代からの官僚)の逆襲を可能にし たのはエリツィンにきわめて近い同盟者と、ロシアの誰よりも狡猾なオリガリヒ(新興資本家)であった。それはすべて、1999に始まった。当時、彼らは、 一介の旧KGBマンを表舞台に引っ張り出してクレムリンにすえ、そうすることによって自己の遺産を確保しようと考えたのである。 シロビッキ(内務省、旧KGBなど武力省庁の当局者)の権力上層部での割合は、ゴルバチョフ政権下の4.8%からプーチン政権下では58.3%と急激な変 化を遂げた。 「シロビッキは社会的地位や精神構造の点で非常に均質的な集団です。シロビッキは、自分たちが国家の利益のために行動していると考えており、ロシアが再び 恐れられる存在となることを狙っています。愛国主義や経世の才と称していますが、厄介なのは、彼らの心の中で強い国家という概念が恐怖心をかもしだすこと と結び付いている」 エリツィン時代の混沌状態で、無政府状態、汚職に対して集団的秩序復活の願望が生じた。不公平な資産分配とファウスト的取り引きがプーチンの台頭を促し た。法律の枠組みが不完全であり、法治の貫徹という高潔な見せかけのもとに国家統制を導入するのに理想的な環境であった。 (国際連帯) たしかに、この地域での覇権を求めない国家にとっては、「ロシア関係の書物の出版に逆風が吹いている」のも当然であろう。 国家の首脳がこのような状態であり、本格的にアジア〜ユーラシア大陸に腰を据えた国益追求など虚しくなってしまうかのようである。 無制限にアメリカに追随し「アメリカの傭兵の死」によって国民感情を共感・共振させようとするこの国に良く見られる劇場型21世紀モデルは、アメリカ人・ ブッ シュと同様に、「世界への無知」をさらけ出す。 |
 トップページへもどる
トップページへもどる