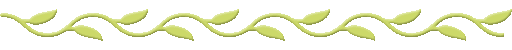
ベトナム戦争全史
|
 |
| 目次 | |
| 著者まえがき 日本語版へのまえがき 例言 序章 第Ⅰ部 戦争の起源-1960年まで 第1章 ベトナム・危機への道 第2章 1945年までの共産党-恐慌から戦争へ 戦争が勃発した時、党派そのメンバーを農村地帯の地下活動に再編成したがそれでもコミンテルンの政策に忠実であった中心的指導者を含む2000人以上の党 員が逮捕された。もっとも共産党以外の反植民地主義者の小集団はすべて牢獄の中や外国に姿を消してしまうか、支配者との協調に転向してしまったので共産党 にはライバルがいなくなってしまった。 さらに重要なことは、党の新しい指導者がベトナムの現状をまずもって重視するというホーの信条に政治的にも個人的にも親近感を持つセクト的で無い人々に よって占められたことである。 この時以来結束が固く協力的かつ創造的で、しかも利己主義の問題から解放された指導体制が登場し、それはその後40年にわたって指導部の連続性を支えるこ とになた。彼らのあいだの調和は党の力の基本的な源泉となり、他のマルクス・レーニン主義党を悩ますことになる指導体制の混乱をベトナムの党が回避できた 基本的な理由にもなった。 第3章 ベトナム・1945年8月革命から長期の戦争へ 第4章 ベトナム共産主義の内部世界-その理論と実践 党の統制を超えたところにある歴史の構造的な発展と客観的な法則が、潜在的には革命の可能性のある状況を形成した。それに正しい考えと決定を導く党の明晰 で意識的な努力が結合し、両者が弁証法的に相互作用を及ぼしてはじめて、現実に革命を可能とするような質的に新しい状況が創造されるのであった。 こうした考えによれば歴史の変革を熱望するならば、人間はその事業がいかに、またなにゆえ困難で、時間のかかるものか自覚していなければならなかった。実 際のところ、みずからの限界をわきまえることこそ自らの可能性を知る上で決定的であった。 歴史は党がその願望を自由に書きこめるような白紙の小切手ではなかった。しかし同時に政治的な人間が活動をやらなくても良いような、本質的に非人間的な過 程でもなかった。 まず第一に社会の諸勢力が確認され動員されなければならず、党の前衛としての役割は、誰を何に向かって導くのか理解することと結びついていた。このことは ま た大衆から学ぶことを求めおり、それは不可避的に党が大衆を指導するためには、時に応じて党が社会勢力の動向に従わざるを得ないという党と大衆との共存関 係を意味していた。 第5章 共産党の権力強化 第6章 アメリカ、世界強国の限界と苦闘-1946~60年 (帝国主義の相続者の責務と使命) 1945年以降のアメリカの対外政策を特徴つけたものは、第二次世界大戦のもたらした混乱と植民地体制の残滓から統合された本質的に資本主義的な世界秩序 を創造しようとする、世界大の強力なコミットメントであった。アメリカは現代史における帝国主義の装いの主たる相続者であった.アメリカは自己の物質的な 繁栄にたいするなんらかの有形の脅威に対して国家を防衛する願望から行動したのでなくて、遠隔地の政治的運命がアメリカの国内社会の当面の必要をはるかに 超える目標や利益にとって有利な形で推移することを可能にするような、コントロールができ、かつ思い通りになる秩序を世界中のあらゆる所に構築しようとし たのである。世界の管理はアメリカの力こそが可能にすると信じられていた贅沢と、必要性であった。そして、うまくいけば、このことがアメリカにより大きな 繁栄をもたらし、将来も約束するであろうと思われた。そのために不可避的なコストは以前の全ての帝国主義国と同様、国際的責務と使命の履行として正当化さ れた。 第二次大戦後の歴史は本質的にこのような世界秩序を組み立てようとするアメリカの途方もない試みと失敗の歴史であり、同時にそのアメリカの野望に対抗して 世界中で起こった本質的に自立的な社会諸勢力と不安なダイナミズムの歴史であった。 (法外な願望と限りある資源の優先順位) こうした野望のためにアメリカはアメリカ自身にとって最も重要な問題でありつづける課題に、直面することになった。それは、法外な願望と限りある資源の対 立であり、優先順位をどのようにするかという問題であった。 (優先順位と指導者の尊大な信念) 現代アメリカ外交史の大筋の課題は,複雑な世界とアメリカの力の限界、及びワシントンの指導者の幻想と無視を含めた認識との相互作用であった。 世界の政治的・経済的問題、社会的ダイナミズムは一国はもちろん幾つかの国が束になっても統御できるものではないことを認識しようとも思わなかったし、認 めることもできなかった。 1947封じこめ戦略 1950巻きかえし戦略 1954ドミノ理論 顕在化しつつあったベトナム問題が他の多くの国際問題と結びついたのは世界戦略とドクトリンの模索という大きな文脈の中であった。 第二次世界大戦 第7章 1959年までの南ベトナム-紛争の起源 第8章 南部における共産党のジレンマ-1954~59年 第Ⅱ部 南ヘトナムの危機とアメリカの干渉-1961~65年 第9章 合衆国のベトナム介入-支緩から北爆開始まで 第10章 戦争とベトナム農村 篇11章 軍事戦略の設定をめぐる挑戦 第12章 合衆国と革命側、そしてたたかいの構成要素 第Ⅲ部 全面戦争および南ベトナムの変容-1965~67年 第13章 戦争エスカレーションとアメリカ政治の挫折 第14章 効果的軍事戦略の継続的追求 革命側にとってきわめて重要な戦略的主導権の維持が可能であったのは広大な南ベトナム全土にわたって米軍とベトナム共和国軍を分散させる力を持ってお り、また米軍分析機関も、革命勢力が米軍を消耗させるために分散させる戦略を取っていることを理解していた。 <革命側と敵勢力との共生関係> 南ベトナムにおいて革命側の軍事組織と政治組織が組織的にかなりの規模に達したために兵站物資を地域ごとに自前で最大限調達することが必要となった・・・ 1967年南ベトナムのベトナム人民軍及び人民解放軍の正規兵員数は22万から28万人に達し、うち三分の一はゲリラ部隊であった。これに加えて常備軍に 所属しているわけではないが、約12万の要員がいた。さらに7万5千人から9万人の政治幹部がいた。1972年まで、革命側の戦力は以上述べた範囲で推移 した。 革命側にとって主要かつ決定的に重要な、これら部隊に対する食料と装備は確保された。それが可能だったのは党が1955以降、サイゴン政権内に潜入し合法 的な組織を作り上げて、打倒の対象であるシステムから得られる経済的、軍事的援助をすべて手に入れようと努めてきたからであった。 解放民族戦線とベトナム共和国の支配地域のあいだの経済的共生関係は非常にうまく機能していた。 解放民族戦線にとってベトナム共和国と共生関係を持つことが、戦争を長期化させるうえでも、また主導権を維持するためにも決定的に重要な手段となったので ある。 第15章 アメリカの戦争遂行方法のジレンマ 第16章 戦争と南ベトナム社会の変貌 第17章 グエン・ヴァン・チューとベトナム共和国の権力構造 第18章 経済的従属のジレンマとベトナム共和国 第19章 ベトナム共和国軍の建設と南ベトナム農村をめぐるたたかい 第20章 二つのベトナム軍の性格とその結果 <2つの軍隊の本質ー将校と幹部> ベトナム共和国軍の常習的汚職、公費横領、給与・食料のごまかし、請負業者のピンはね、昇進や安全な地位の売買、ガソリン・医薬品の横流し、戦闘中の輸送 費や支援砲火費の他部隊への請求など多岐にあったが、最も普及していたのは幽霊兵士(戦死者,脱走者、文官職についたままの兵士など)で、各時点で4分の 一に及ぶこともあったと見られ、十分の一を切ったことはいちどもなかった。 ベトナム共和国軍将校の兵士に対する関係は、こうした、ゆすり・たかりの構造を反映していたし、また、兵士と住民の関係を規定した。 戦争が進行し幹部が抜擢されるにつれ、戦闘中の個人的統率力にやや大きな力点がおかれるようになった。幹部は何よりもまず,兵士たちが尊敬し従うことので きる模範的人物であることが要求されたが、また他の人々が過ちを正しやすいように、自分の過ちを公開の場で告白できるものでなければならなかった。 幹部の戒律はかぎりない忍耐と統率力を要求した.人間的高潔さが兵士たちの目に確認されれば、幹部は穏やかな接触を通じて最善を尽くした。命令を発し,規 律を要求する権限を持つことは疑う余地がなかったが、それに訴えれば失敗とみなされた。幹部は兵士の恐怖,不安、孤独,窮乏が厳しい現実であることを熟知 し、「軍律は驚くほど緩やかに見え,命令より説得,処罰より慣用が一般的に適用される規則である」(ランド研究所報告)こうした懸念を努力と連帯で取り除 かねばならなかった。 <下級兵士> 1968頃まで、ベトナム共和国軍将校団は都市的,都市化された性格を持ち、兵士の大部分は農村の出身で、両者の行動,態度,意志疎通上大きな懸隔となっ た。 (軍隊の静態的戦略) 兵士は、1968頃までその23%は軍隊外で追加所得を稼ぎ、(45歳まで軍隊に留まらなくてはならなかったから)46%は家族を部隊内、その周辺に住ま わせていたので、ベトナム共和国軍は兵士のほとんどをその徴兵地の軍管区から動かさなかった。 さらに1968年には兵士の74%が既婚者であり、平均3.9人の子どもを抱えていた。つまり、1968年、妻子は約300万人、つまり南ベトナム人口の 17%におよんだ。兵士と家族は全人口の22%を占めていた。 静態的戦略にくわえ、軍隊事態よりもはるかに多くの身内を抱え、この悲惨な難民の群れは1968以降、絶対的にも相対的にも増大しつづけた。 さらに(この家族制度のため)共和国軍の42%は全く炊事部門を持たず、兵士は食事のためにしばしば金を出し合わなければならず、軍務時間の多くは、そう した困難の対処のために費やされた。 人民解放軍ははるかに小規模な軍隊であったが、選り抜きだった。 幹部は個人的な不安や恐怖を克服するように援助し、また難題に対処する集団的の力と知恵という意識を兵士に与えるように努めた。 自己批判集会は、一部の兵士たちを困惑させ,阻害することがほとんどであった。にもかかわらず、意志の疎通を隔てる壁が取り除かれ、要求と願望をひとつに して行った。公開の自己批判と批判が脱走や戦闘拒否を含む重大な軍旗違反への処罰にかえて行われることもしばしばであった。ひとそれぞれの弱点をおおっぴ らに認めることによって、また集団の力を高めうるのだと党は確信していた。 古参兵と新兵は3人1組の細胞を作り互いに助け合い、生活を共に助け合った。全軍のこの基礎単位は持続性を保ち高い成功をおさめた。 <2つの軍隊の結果ー兵士と社会> 兵士たちの長期戦への確信を崩さないよう行き過ぎた危険から彼らを守った。大隊規模の先頭は年平均2から3回、しかも一般的に短期間にすぎず、もっと頻繁 に行なわれた小部隊の戦闘も先頭の主導権をとり、過ちを分析し正し、必要なら士気を取り戻すことができた。 「生命を愛する革命戦士である。だが必要とあれば喜んで断固として犠牲となる」つまり社会的連帯が献身を要求したのであり,多くの貧しい農民は勝利が家族 ともに村に物質的保障と正義をもたらし、党はもっとも強力な部隊は政治的に自覚した軍隊であることを知っていた。 勢力の均衡や自らの事業の勝機について革命軍へ意志の自覚も極めて重要だった。広範で体系的な政治教育や敵の大火力の利点と限界など戦争の現実的評価を平 均的兵士でも多くを知ってた。政治は自己の将来を理解する環となった。 <ふたつの軍隊の結果ー兵士と社会> ベトナム共和国軍はほとんどが強制徴募されて尾羽打ち枯らした傭兵となった貧民で構成されていた。戦争の中で最も抑圧され,道に迷わされ,ぎりぎりまで追 い込まれた人々であった.革命側は階級的立場に基づいて彼らに呼びかけようとしたが、あまり成功しなかった。なぜなら、アメリカの政策と上官の堕落が彼ら を苛酷な戦争の敗残兵にしつつあったからである。どこにでもいるような、そうした最下層の者の例に漏れず、彼らは他の人々から多く奪った。 この軍隊の戦利品あさりと強奪は農民に途方もない大きな経済的負担をかけた。たんにたえざる略奪の故にでなく,自分たちの息子や娘が同時に被害者であり加 害者であるのを見なければならなかったからである。 こうした状況は莫大な経済的代価を強い、伝統的生活様式を急速に変更させた。1960年代末に解放戦線支持派だった農民のますます多くが,精神的にも肉体 的にも疲れ果て、また残忍な軍事機構に脅かされた結果、消極性と模様眺めが著しく増大した。 集団として彼らがベトナム共和国に忠誠を売り渡すことはなかった。それは、この腐敗と疎外が、伝統的ないし急進的な価値観に満たされた生活様式とは異質 だったであるが、このふたつの価値観は農民に影響を与えていた。 一方で、アメリカ後援の「近代化」の衝撃は、平定努力を無にするような敵意の大貯水池を作りだし,少なからぬ若者がでんとうてきりゆうやじぶんのにんげん せいやかちかんを守りたいとの理由で、引き続き革命に参加していった。 第三世界の軍部は政治的にも社会的にも決して中立の機関ではない。その性格、規模、人間的役割はいかなる従属国にとっても、その政治的,社会的,人間的過 程の統合であり、兵器・兵員の使用法の優劣とした戦闘の道具ではない。しかし、ベトナム共和国軍の増大とともに、社会構造は、その矛盾を吸収しきれなく なった。 第21章 全面戦争への共産党の対応 第22章 アメリカ合衆国への戦争の経済的影響 戦後アメリカの戦略・軍事理論のほとんどがそうであったように、その限定戦争ドクトリンはあらゆる戦略につけられるはずの値札を無視していた・・・皮肉な ことに、兵器から巧みに身をかわし、紛争を無期限に引き延ばす能力を持つ敵を前にして、ベトナム戦争はやがて兵器事態に内在する非効率を露呈した。この技 術的に高度で高価な戦争においては、兵器こそ決定的であることが速やかに立証されなければならず、さもなくば、それは逆にアメリカの力にとってマイナスに 転ずるであろう。 長期戦は不可避的に内部矛盾を生み、いずれそれは決定的ともなりうる難問をひきだす。高価な技術によるゲリラ戦解決法は深刻な経済的行き詰まりをもたら し、やがて重大な政治的、社会的難問を引き起こさずにはおかなかった。 第23章 1967年末の戦争における勢力均衡 第Ⅳ部 テト攻勢と1968年情勢 第24章 テト攻勢 <攻勢へのアメリカの備え> <攻勢の開始> 革命側の計画はフエを除けば,地方軍と工兵隊を持って5日間まで都市を襲撃し、その間正規軍は近郊に待機するというものだった。民衆の蜂起や南ベトナム陸 軍の総崩れがあったなら,戦闘は規模を拡大したろうが,蜂起は起こらなかった。 残虐な戦闘と火力の無制限の使用という状況で都市蜂起に類したものは起こらなかった。攻勢があたかも決戦であるかのような行動に駆りたてた幹部たちの努力 が突出したため、都市の下部組織のほとんどは攻勢が始まると同時に死亡または逮捕されて、党指導部を愕然とさせるほどガタガタいなってしまった。そこで、 絶対的に必要とされる以上の勢力の投入をためらった。 革命側の攻勢は都市蜂起を除けば,当初の主要なの目的を達成した。都市蜂起が起こらなかったのはアメリカとベトナム共和国に抵抗するもの全てに向けられる 途方もない火力の故だけでなく,そのための政治的前提条件が存在せず、またどっちつかずの同調者たち-その数は多かったがー生命の危険を冒そうとしなかっ たからである。 第25章 テト攻勢の衝撃、ワシントンにおよぶ 第26章 テト攻勢の評価 (解放民族戦線の地域への創造的適応) 解放民族戦線の組織は創設以来分散されていたー連絡の問題や戦時の分断の問題がある以上ーそれは避けがたいことであった。そして、これこそが創造的適応の 源泉であったが、それはまた一方で村落組織をますます攻撃にさらすことになった。 多くは公的地位を持たない草の根の活動家で,彼らなくして屈せず革命を持続することは不可能であり、そうした人々は多年の経験と共に,地方の村落と彼らが 共に生活する村民とのこじんてきでしばしば家族的な接触に基づいていた。その重要性ははかりしれず、かれらは他の一切を産み出す結合力を与え、あらゆる次 元の闘争の中心となったのである。 (ところが)CIAは下部要員,同調者,臨時の活動家あるいわ収税人を解放戦線の下部組織とみなすことを潔しとせず,フェニックス計画が1968年に1万 3千人という多数を逮捕,殺害したにもかかわらず、計画は失敗しつつあると考えた。下部組織が実際には大部分みずから動機ずけをなし、自律的に活動するよ うに明確に奨励され、そうした幾千の下層、無名のひとびとに依拠するようになっていたとき、それが正規の作戦司令体系に充足していると確信して,何よりも 高級幹部を追及したのであった。 しかし、革命側は、そぼ下部組織が農村で手ひどい打撃を受け,都市では大量に抹殺されつつあり、今後数年間はこうした形で損害が続くことを知っていた。 第∨部 戦争と外交-1969~72年 第27章 ニクソン政権、ベトナムおよび世界と対決 <ニクソン政権の移行期> <ニクソン政権の時間稼ぎ> <ベトナムとアメリカのグローバルな優先順位の拘束> <エスカレーションとベトナム化> 多くのベトナム政策・にわか芝居・実験などがいきあたりばったりぶりにしか見えないとしても、その最終的な意味と目標がホワイトハウスにもわかっていな かったとしても、その行動を下支えしていたのは、アメリカが受諾可能な解決を勝ち取るまで他の問題やコストに打ちのめされず戦争を引き伸ばすことにより、 アメリカの力への「信頼性」を長期に維持しなければならないという固い信念であった。 尊厳意識や国際的イメージを満足させるために、十分な外交儀礼とまわりくどい言いまわしのうちに撤兵を忍び込ませるしかなかった。 また、ベトナム化や大国外交が解決に妥当かを実験したりもした。 (キッシンジャーのエスカレーション策)ベトナム民主共和国を交渉に引き込むことが可能だとする信念から、1969年からの戦争の段階的拡大を計り、 1970にはカンボジア・シアヌーク政権へのクーデターも支援した。アメリカは戦争をさらに拡大する願し,頑迷に見えるチャンスとみえたのである。しか し、カンボジア侵攻は全インドシナへの戦争の拡大であり、準備の整わないベトナム共和国=アメリカの軍事.政治ラインは伸びきってしまった。南ベトナム外 への米空軍力と南ベトナム陸軍の転用による空白は革命側が埋めたのであった。 さらにラオスへの南ベトナム陸軍の侵攻(ランソン719号作戦)はカンボジア侵攻と異なり、準備を整えた革命側の努力により大敗走となり、南ベトナム陸軍 と米空軍力の弱体化を見せつけた。戦争拡大による時間稼ぎは、たちまち矛盾をさらけ出した。軍隊を撤退させつつ,一貫性のある軍事戦略を確定することは不 可能であり、たださまざまの軍事問題をごたまぜに積み残しただけである さらに重要なのは,戦争の結果カンボジアを20世紀で最も荒廃した国に変えてしまうことになる戦慄すべき破壊症候群をホワイトハウスが示しはじめたこと である。 第28章 アメリカ軍事力の危機 <アメリカ軍事の限界> 1969年軍事戦略は撤退向けに調整され、地上での大規模な攻撃活動を控えた1970戦死者は1968年当時の三分の一となり、兵力が68年より半減した 71 年には戦死者は十分の一を割った。米陸軍は急速に実戦用戦闘力ではなくなった。 ニクソン政権の代替策は空軍力と砲兵隊であった。キッシンジャーやニクソンはエスカレーションを政治目的のために用いるとし、爆撃トン数はワシントンの軍 事戦略の最後の1本となっていった。しかし、現実の爆撃は、決定的に重要な軍需物資の流入は阻止できず、敗北回避というより,敗北隠蔽の方法になっていっ た。空軍力によるエスカレーションは軍事バランスに影響を与えるとは、革命側も軍の専門家も信じていなかった。 <米陸軍の危機> 一般的傾向として、グランツ(海兵隊の歩兵たち)など前線おくりには教育水準の低いものが選ばれた。1968~1970、死傷者の62%は徴募兵で,教育 歴10年以下の兵士の損耗率は13年以上の3倍,所得4000から7000ドル世帯出身者の損耗率は17000ドル以上世帯の約3倍となっていた。 1968年以後小隊は可能なら「射撃戦や索敵をせずやり過ごすこと」が一般的に認められ「索敵逃走」(戦場の部隊による暗黙の戦闘回避を意味する)が事実 上の戦争原理となっている」「CYA(後生大事に)国へ帰ろう」というGI用語がいききと言われていた。 <軍隊内部の退廃と抵抗> 1973ペンタゴンは南ベトナムの駐留した全陸軍兵士の35%がヘロインを用いたことがあり、20%は勤務中にヘロイン中毒にかかっていたことを認めた。 もちろんマリファナ使用のほうが一般的であった。1972初頭,いくつかの重要な米軍基地は麻薬の使用を押さえたいとの願いから兵舎に買春婦を入れること を許可しはじめた。 第29章 革命側の軍事政策-1969~71年 政治局は1969春、テト後の革命側の弱点と困難を認めた。テト攻勢が決定打になるだろうと考えたものは当時、意気消沈のあまり必要な時に行動できない者 と並んで批判された。もちろん、実際にはテト前の党の立場の微妙なあやは、時間をかけて注意深く検討したものにしかわからなかった。 確実なのは、あまりにも大きな犠牲が攻勢に加わって生き残ったものを呆然とさせたことであり、攻勢が戦争を終結させなかったという失望によって彼らの悲し みは倍化したのであった。テトの英知は政治局がかつてくだしたいかなる決定にも増して広く疑問視された。なぜなら情勢は戦術的にずっと困難かつ危険にな り、はるかに大きなその戦略的優位によっても物理的に緩和されなかったからである。 南出身の革命軍の半分までが1968年中に失われたというアメリカ側の推定・・・1969年に人民革命軍とベトナム人民軍からの脱走はピークに達し、ふた たび低水準に戻ったのは1971年のことであった。 <新たな軍事的均衡を創る> 革命側は大攻勢の機が熟し実現可能になるまで人員と物資を温存しつつ南の部隊と勢力の立てなおしに専念することを決定した。 1969年秋、南のベトナム人民軍は中退規模に分割され、ついでにその一部は工兵部隊に編成替えされた。これらの中隊は、すばやく再編されて主力軍大部隊 としてたたかうこともできる一方、補足しがたく、効率的でもあった。 大部隊として展開する場合でも彼らは小部隊に分かれ、やむをえない場合以外、戦闘を拒否するのが常であった。 また革命軍は近代化しつつあると同時に、地雷や落とし穴など遊撃戦の初期の原始的な形態への依存度も高めていった。 一方、1970年1月党中央委員会は主力軍の構造を改善することを検討、実際1970年はじめにはベトナム人民軍の戦車と大幅に改良された火力が中部高原 に姿を現しはじめていた。ソ連と中国の軍事援助によって可能となったが、いずれにせよ1972年まで攻勢を延期することで戦闘能力を劇的に改善した。 先端技術に痛手であったのは、革命側の防空能力が次第に改善されたことだった。アメリカ軍は1969年はじめ連発力を増し、破壊力を高めた51口径高射砲 との遭遇を報告した。 政治的主体としての革命軍の真の力量は状況に迫られて、小規模な分権化した部隊への分散を余儀なくされたときにあらわれる。 現地解放民族戦線のこの強靭性は依然として大きな軍事資産であり、多くの敵を釘付けにし、他地区での革命軍の発展に時間と自由を与えたのであった。 政治は、本質的に粘り強い、自立性の高い人々で構成された初期の村落での党の政治と変りはなかった。 軍事的方程式に変化が生じたにせよ、装備の面で劣った革命側の攻撃戦略を可能にしたのは、その場、その場に応じてなんとか切り抜け、機動力と柔軟性をもっ た地方遊撃隊員と政治幹部に依存し、数十年にわたって党員に注入されてきた地方組織の自立的で自ら動機付けできる性格によるものであった。 第30章 アメリカとベトナム共和国-ベトナム化の矛盾 第31章 変貌する南ベトナム農村をめぐる闘争 <フェニックス計画と平定> 「できるだけ多くの共産主義者を殺したい」 <チュ-と土地改革の複雑さ> <土地の変化と農村危機の前兆> <長期戦のジレンマと農民層> (住民にひろがった消極性=生き残りの政治学) 長期にわたる流血の戦争が南の農民層とその社会に及ぼした影響を総体として叙述することは不可能である。なぜなら多年の破壊,人口移動,そして恐怖政治が 革命側もアメリカも共に関わらなければならなかった政治的宇宙をひどく変えてしまったのである・・・仮借ない、いつ果てるともしれぬ重圧は彼らを別な論法 に適応させ始めた・・・ <平定への革命側への対応> フェニックス計画がその組織者たちの知り得た以上に成功を収めたことは間違いない。計画はきわめて分権的な政治活動を大きく変えるほど多数の下級幹部を逮 捕した。主要な問題は実際の逮捕や堅固な要塞からの排除というよりむしろ,解放戦線の地方軍にしみこみ始めた全般的な疲労と士気の低下であった。軍事的側 面と政治的側面は相互補強し合ってきたが、党が政治活動より軍事活動を重視し、正規軍が戦闘を回避している以上、政治活動家の気力低下は理解できることで あり、党は情勢を支配する力をうしなうことにつながった。 第32章 共産党の国際戦略 <中国とベトナム戦争> 中国では三つの党派が政策の主導権をめぐって争っていた。軍部はアメリカの戦争エスカレーションを懸念し、しあkもソ連との対決を回避しようと、南ベトナ ムの戦争の長期化を望んでいた。文化大革命の急進派は純然たるイデオロギー路線を堅持し、最後に周恩来の穏健派は、脅威はソ連のほうが大きいとみなし、ア メリカ政府との関係改善に期待していた。 <ソ連とベトナム戦争> <世界で新たな革命的役割を求めて> ベトナム民主共和国にとって中ソ対立という危険な障害があり,しかもアメリカがその可能性を利用する可能性があるなかで、この両者をうまく切りぬけていく ためにはするどい分析力とずば抜けた手腕が必要であった。全面的には信頼できず、かといって中ソの援助なしにはたたかうことができないという,不安定な立 場に置かれていた。 1965から1968までベトナム民主共和国領内には中国兵站部隊が駐留していた。32万人が派遣されていたと後に言われたが、実数はこれほど大きくな かったにせよ、輸送を確保する上で実質的に死活的役割を果たしたことは間違いない。 多くの経験を積んで中ソに対する素朴な信頼感が失われていったものの,党はイデオロギー上の問題から国際的団結を回復させる必要があると考えていた。しか し分裂は変更不可能な現実であった。このような問題が頂点に達したのは,アメリカがデタント外交によって中ソの矛盾を利用することを真剣に考えてきた時期 でもあった。塔はベトナムは世界革命の最前線にた「自主独立と創造性」の精神を持って共通の敵と対峙していたが・・・このイデオロギーが今後も有効性を保 持できるかどうかは事態の推移を見ないと分からなかった。なぜなら,中ソ両国が幾度も理想を裏切る状況では、非現実的に思えたからであった。 しかし、ベトナムは汚れなき世界規模の運動を包み込んでいた。こうした理想主義のもと、無数の人々が反応し結集したのである。 第33章 二つの前線での戦争-外交と戦場、1971~72年 1969年12月、中国はアメリカとの正規ルートの対話を同意した。この米中対話は米ソ両国が国際-ベトナム問題の進展をもたらすことができなかった結果 であった。中国は予想されるソ連の敵対行動(ソ連はニクソン政権に協同で中国の核兵器施設に対する攻撃を非公式に打診したことがあり、1969年末にはソ 連自身が中国の核兵器施設攻撃の1歩手前までいった)を抑制するためアメリカの強力を求めていた。 勇気付けられたニクソン政権は、1969年末にはベトナム民主共和国の頭ごなしに遂行していた三極外交戦略や戦争エスカレーションによる威嚇政策、そして 「ベトナム化」政策(これらは,互いに時間稼ぎの状況を作り出すことによってそれぞれの政策を進めやすくしていた)が成功する可能性があると考え,その後 三年間にわたってニクソン政権の政策を支え、その政策を導いたは、このような願望であった。 第34章 和平交渉の過程-幻想と現実 第Ⅵ部 ベトナム共和国の危機と戦争の終結-1973~75年 第35章 1973年初頭における南ベトナムの勢力バランスとベトナム共和国の政策への影響 第36章 ニクソン政権の力のジレンマ 第37章 復興と対応-1974年半ばまでの共産党の戦略 第38章 ベトナム共和国の社会体制の危機の深まり <ベトナム共和国の政治秩序> <ベトナム共和国の政治的正当性のジレンマ> ベトナム共和国軍は20年の間,都市住民を自らの大義のもとに結集する努力をほとんどしなかった。都市イデオロギーは,消費やナルシシズムー都市住民,若 者に浸透していたーから自然発生的に産み出されたものであった。たとえ都市住民の多くが革命側に慎重な態度をとっていても、チュー支持の社会的コンセンサ スは存在しなかった。チュー政権存続は、アメリカからの援助ー将校やエリートの支持の獲得と、同じく都市の大衆に食料を保証し従順な態度を取らせること に、かかっていることが明らかになった。 <従属的秩序の経済危機> ベトナム共和国の究極の崩壊をまねく十分な条件を生み出したのは経済であった。 インフレは緊急な問題であった。1972年26%。1973年45%。1974年63%。 さらに1974年に都市労働者の三分の一が失業していた(米国際開発局推定) <ベトナム農村と従属性の帰結> ベトナム共和国は外国の援助を援助を獲得する以外にプランはなかった。 戦闘を縮小すれば対応できる軍事援助と違って、経済援助は急速に悪化するために増大させなければならなかった。しかし、問題はホワイトハウスも議会も援助 を出し渋っていた。 アメリカの援助の他に、世界銀行、IMF、アジア開発銀行など国際金融機関の利用が検討された。これはニクソン政権にとっては自ら支出せず、援助にうるさ い議会の統制を回避する手段であっ たが、ただちに困難な場面に直面した。 奇妙で非現実的だったのは、石油開発によってベトナム共和国の崩壊を防ぐという空想であった。 「われわれはエッソ,シェルやモービルを頼りにしなければならなし、彼らがきょさうん勢力に反対の立場をとることを信用しなければならない」 「石油の発見は南ベトナムの抱えている経済問題のすべてを解決するだろう」とチューの側近は述べたが、このような幻想は破滅的な政策をさらに助長するだけ であった。 <アメリカ政策立案者の経済危機への対応> 第39章 サイゴンとワシントン、1974年半ば-二つの危機の結合 第40章 1974年後半における革命側の認識と構想 第41章 戦争の終結 1975年初め,火砲は1400門に400.戦車や兵員輸送車は1200台に600台。航空機は1400機以上。戦闘部隊18万5千人、支援部隊10万7 千人,ゲリラ部隊4万5千人と推定される革命側に比べ、共和国軍は戦闘部隊で2倍,全体で3倍勝っていた。 また敵の9倍の砲弾を利用でき、ばくだいな在庫があった。 結語 アメリカの敗北はたんにその軍事力の失敗というにとどまらなかった。 アメリカは代理人に軍事力を肩代わりするのに部分的に成功したけれども、(限定戦争理論や第三世界に干渉する技術)・・・アメリカが軍事的成功の前提諸条 件を実現するに足りる政治的、経済的、イデオロギー的な実行ある体系を本来的に創りだし得なかった。 がきこくに支援された社会の数えきれない弱点・・・アメリカが植えつけようとした個人主義と利己主義はアメリカ自身のイデオロギーと社会体制の反映であ り、私的所有と富の蓄積の奨励は、公然たる反革命イデオロギーを必要とせず、ただの生活スタイルであったが、軍事行動と社会制度に関する革命側の本質的な 諸価値には拮抗できなかった。 アメリカは腐敗し、脆弱で、移り気な住民を金で買っていたから、この対策は本来的に自滅的であった。 30年にも及ぶ党の最も重要な力の源泉は、社会主義的、革命的道義性という党の考え方と社会主義社会の実現と具体化のためにラディカルな価値及び行動を 基本的に終始重視するという立場であった。党員の生活をこれらの原則によく即応させるような組織造りをする党の能力が、このような目標を機能的に達成させ たのである。 個人のきわめて重要な役割についてのこうした考え方は、マルクス・レーニン主義へのベトナム共産主義のもっとも顕著かつ基本的な追加であり、指導者及び純 組織規律の相対的な重要性に関する原則の暗黙裏の修正であった。 異常なほどの個人的な献身と犠牲、極端な窮迫としばしば孤立という条件のもとで何十年もたたかい抜いたことは、このような革命的な献身と価値~それが急進 的神秘主義やロマンティズムにならないように力のバランスを無視しないで、個人の責任と行動との決定的役割の重視した革命的道義性~の影響力を評価するこ とをぬきにしては、理解することはできない。 (それというのも、戦争中の戦略戦術は、成功の必要条件であっても充分条件ではなく)多面的な聞きが指導者を含む誰の予測能力を超える形で情勢を左右する 長期の闘争では、究極的な党の力は、耐える力であり、また正しかろうが間違っていようが、情勢に対応しつづける能力であり、粘り強い献身的な党員の存在が 党に賦与したのである。 |
 トップページへもどる
トップページへもどる