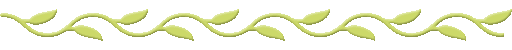
日本憲兵正史
日本軍中央部の反省と憲兵の自己批判(戦犯)
|
| 日本軍中央部の反省と憲兵の自己批判(戦犯) | |
| (日本軍中央部の反省) 軍は「生きて虜囚の恥ずかしめを受けず」との戦陣訓を告布して、俘虜となることを戒め、将兵もまた俘虜となることを最大の恥辱と心得ていたため、わが国将 兵の俘虜は動員数に比較して極めて少なく、したがってわが軍部は俘虜に対する関心が薄かった事は事実である。 一九四八年の赤十字国際委員会の報告書は、「日本官憲は自国民俘虜には殆ど関心をもたぬから、外国人俘虜には非常に苛酷であった。若干の日本高官は、ジュ ネーブ条約の実施を企てたが、人道的原則の価値を否定 する軍官憲によって阻害された」と記述しているが、軍中央部は国際法を軽視するきらいがあった。 昭和十八年、ポルネオにおいて発生した、赤十字代表フイッシャー博士夫妻(スイス人医師)の反逆通諜事件に対し、日本政府はその資格を認めず処刑してい る。これは消し難いわが国の恥辱である。 また、軍中央部が、国際法尊重の観念が薄いにもかかわらず、昭和十七年一月、外務省が在米邦人保護のため、国際法を準用する旨を通告したこどは、後日多数 の戦犯者を出す原因ともなった。 さらに昭和十七年四月八日、東京空襲にあわててその対策に苦慮した軍部は、同年七月二十八日、陸密第ニニ九〇号、同十九年、陸密第九○八七号の「敵機搭乗員に関する件通謀」を以て、違反者を軍律会議に付すように指示した。こ れら搭乗員の行った無差別爆撃は、明らかに国際法 違反であり、幾十万という非戦闘員の生命が奪われ、死屍累々として肉親、住居、財産を失った避難民が街を埋める惨状は眼を覆うものがあった。陸達の趣旨も また当然と肯定せざるを得ないが、この通達があったため、各地の軍司令官は軍律会議に付すことなく独断処刑を命じ、あるいは 南方戦線その他において、人跡まばらな島嶼を空襲した搭乗員を捕え、惰性と陸達の趣旨を曲解し、無裁判処刑した例もあり、現地の実情やむを得ぬものありと はいえ、多くの戦犯者を出した。 また、軍中央部は原住民の保護処遇、その他において適切な指導監督を怠った。 その最たるものは支那事変下における南京事件である。あの膨大な数字には問題があるが、虐穀の事実は否定できない。この事件は英書その他に公表されて、日 本の悪名を高め威信を失墜した。この事実は、日本政府を始め軍部も承知のはずであるのにもかかわらず、単なる抗日分子の粛清ぐらいと受け取ったのか、徹底 的に事実を究明し、責任者その他を厳罰に付し、将来を戒めるの処置を怠った。 戦場の拡大にともない、南方各地において、いわゆる粛清に名をかりた行き過ぎた処荊が行なわれ、多くの戦犯者を出すに至った。 その他、泰緬鉄遣の建設には、英蘭両軍俘虜多数を使用した。この鉄道はわが軍がビルマに軍需品輪送のため建設を急いだものであり、作戦行動に関係なしとは いえないが、一面その地方の文化向上に資する大義名分がなかったわけでもないが、東京裁判では国際法違反となり、かつ俘虜虐待を指摘された。 この鉄道はかって、英国が建設を断念した難工事であり、湿地しかも雨期を押して強行され、給与の不良、医薬品不足に加え、伝染病多発し、多数の俘虜労務者 が死亡した。この責任を間われ、後日俘虜収容所、鉄道連隊等 に多数の戦犯者を出した。 大本営命令を以て俘虜を使用し、かつ建設を急いだことに対し、軍中央部もその責任を負うべきであろうと考えられる。以上のように、軍中央部における国際法 の軽視と、俘虜の取扱い、原住民の保護処遇、その他に関し適切な指導監督を怠り、将兵もまた優越観や慢心と惰性に禍されたことが原因となり、予想し難い多 くの不祥事件を摘発され、不幸な戦犯者を多数出した。 もとより敗戦という現実の上からまことにやむを得ないものもあったが、軍中央部としてもその責任の一半を負うべきであると思う。 しかも、泰緬鉄道の建設が俘虜虐待となり、ソ連によるシペリヤ地区の日本軍俘虜への処遇が虐待にないらないのは、明らかに勝者の不正義である。 (憲兵の自己批判) 憲兵は軍の擁護者であり、軍内唯一の監軍護法の兵科、すなわち法秩序の惟持者、法の遵守監視者でなけれぱならなかった。 ところが、作戦軍においては、憲兵も最高指揮官である軍司令官に隷属するという身分関係もあったが、軍命令等に迎合するの余り、憲兵本来の任務遂行に欠け るものがあった。軍行動の行過ぎや、法の軽視、または無視に対し、厳然たる態度を以てこれを是正ないしは矯正できなかったがために、多くの不祥事件を発生 させ、多数の戦犯者を出した傾向があり、憲兵としてもその貴任を負うべきであろうと思う。 1、中支において軍司令部が計画実施した俘虜引回し、処刑事件に対 し、憲兵も軍命令を遵守してこれに協力、多数の戦犯者を出した。俘虜の引きまわし等人道に反する計画に対しては、速に軍に意見具申してこれを中止させるべ きであった。 当時、住民の感情その他の事情がどうであろうと、古代を思わす野蛮な行為を中止させることのできなかった責任は、護法の責任を持つ憲兵として反省を要する 点であろう。 2、南方占領地、特に島嶼等においては、敵機搭乗員を軍律会議にかけることなく処刑した事件が多発した。これは軍法会議との交通杜絶、法務官不在等やむを 得ぬ事情は存在したが、やはりどのようなものにせよ裁判を実施させる 意見具申を軍になすべきであったろう。 軍命令なりとして、憲兵自ら無裁判俘虜を処刑した事実は、法秩序維持の 責任ある憲兵としてうなずけないところである。また、俘虜の処刑について、連合軍は戦犯裁判において斬首したとして残虐性を指摘した。これも軍律に死は銃殺と明示されているのであるから、これに従うぺきであり、執行方法 についても憲兵は意見具申をすぺきであった。 3、マレー地区において最大の事件といわれたシンガポール粛清事件は、軍の強硬な意図によって実施され、憲兵隊長も一応は処刑を延期する意見具申をした が、軍は次期作戦のため警備兵力極限の配慮から、これを受けいれられず不幸な結果を招いた。 この事件は戦後遺族に対する血債という形で一応のけりをつけたが、日本軍の汚名は永久に払拭できず、長く友好感情を害している。当時の憲兵隊長が強硬意見 を具申し、職を賭してもその非を称え、あるいは命令を拒否する等、渾身の努力を傾注してこの阻止に挺身すべきであった。軍命令万やむなしと安易に命に服し たことは自省すべきである。その他、南方各地においても、部隊が実施した粛清事件に憲兵が協力しているが、やはり以上の趣旨によるべきであった。 ところが、このような反省も戦後言論の自由を得て始めていえることなのであって、戦時中、マレー方面において飛ぶ鳥をも落とす勢いであった辻政信参謀のよ うな軍内の実力者から、軍司令官の命令である(事実はそうでなくても)、と強引に命じられてもなお、憲兵の本分を逸脱せずに、強硬な意見具申ができる憲兵 はそうはいなかったであろう。それでなくとも、軍参謀と憲兵の問には多くの精神的、思想的対立があった。それは作戦上の勝利を目的とする軍幕僚と、監軍護 法を使命とする憲兵の宿命的な対立であった。事実、憲兵の意見具申を、軍への、あるいは作戦への製肘、千渉と非難する参謀が多かった。 そしてこれらの参謀の中にも監軍護法に理解のある正義の士も決して少なくなかったのである。けれども、幕僚上層部に、目的のためには手段を選ばぬ幕僚を もった軍の憲兵は、ついにその被害者となったのである。 4、昭和十八年、シソガポール港に碇泊中の軍用船数隻が、海上より潜入した濠州軍将校以下の工作員によって、爆破撃沈された事件が起こった。当時の憲兵分 隊長は、工作員の潜入は俘虜収容所にある英軍俘虜の手引きによるものと推定し、部下に捜査を命じ、かつこの犯人を検挙し、自己の功績を立てるために捜査を あせり、極度に部下を叱咤督励したので拷問も行われた。 俘虜収容所内においてラジオを所持していた英人二名が、工作員の手引きをしたという筋書きの下に事件をまとめ、軍律会議に事件送致した。 終戦後、この事件が戦犯に間われ、憲兵隊長が真実を自供せず自ら責任 を採らなかったことが原因となって、死刑八名、無期三名、有期刑三名という大量の受刑者を出した。本件は多分に憲兵将校個人の人格問題であるが、いやしく も自己の功績を誇りたいがために、部下多数に苛酷な迷惑をかけた事実は、自らの死を以てしても到底償えるものではないだろう。 5、憲兵の受けた戦犯裁判の大多数はスパイ検挙,原住民の抗日、反逆分子検挙の際における拷問、虐侍がその殆どを占めている。将校では、憲兵分隊長または 特高課長等の職を奉じたため、監督責任を間われて重刑にせられた者が多い。これら将校の中にも異民族に対する優越感や、少々の拷問は当然なりと、これを放 任または黙認し、適切な指導監督を怠りた者もなしとせず、全憲兵将校が本気で部下の指導監督に当たっていたならば、あるいは憲兵の戦犯者も半減したであろ うと考えられる節もある。 憲兵下士宮、兵も、また、真に憲兵の任務遂行に崇高な奉公精神のみであったろうか。自己の功績をあげるために、無理な取調べをなし、あるいは取調べが拙劣 なるがゆえに拷問が行われたとするならば、自ら戦犯への道を選んだことになる。異民族に対する取調ベ、ことに通訳を使い、あるいは人種、思想を異にする者 に対する取調べの困難さは、深く考慮の余地はあるが、このように多数の憲兵の戦犯者を出したことに対し、下級憲兵といえども自戒反省がなければならないだ ろう |
 トップページへもどる
トップページへもどる