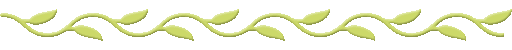
日本憲兵正史
厳重処分
|
| 厳重処分 | |
| 戦前、戦後をとおして、憲兵が最も非難された行為の中に、満州の憲兵隊が行った厳重処分という名の処刑方法があった。これは憲兵が逮補、調査した容疑者または犯人を軍法会議、軍
律会議(現地人の場合)等の裁判に付さず憲兵隊が任地最高指揮官の認可を得て、裁判をせずに処刑する ことである。ところが、これが一時期に、特に軍司令部師団司令部不在地域において、憲兵隊司令官または憲兵隊長の責任において実施されたところに多くの問 題があった。 1この場合、憲兵隊の調査に間違いがなけれぱ、悪法としてもまだ救いがあるが、もし、無実の人間を裁判にもかけずに処刑したとなると、人権問題として非難 が起こるのは当然であろう。 ところが、厳重処分は軍法にはない。それではどうしてこ のような悪名高い法律に準ずるものが生まれ実施されるようになったか、それには次のような複雑な事情があった。 昭和七年三月一目の満州建国後、関東軍は新政府に反対する旧張学良系の残党掃討作戦をつづけた。相手はいわば関東軍に降伏しなかった、旧東北軍であったに 過ぎない。 ところが、この敗残兵が関東軍の追撃にあって次第に分散化し、従来の土匪と結合したり、自ら匪賊化して治安は著しく乱れた。後に集団的な反日軍人の多くは 帰農して農民となったが、それまでには、まだ、かなりの時間が必要であった。 そもそも、満州の馬賊は、第一次世界大戦後から昭和初期の世界的農業恐慌のあおりをくって、食えなくなった農民が、生きるために、自衛用の武器をとって馬 賊の群に投じたことから、集団的な発生となった。これが第一次満州馬賊の誕生である。次が満州事変によって、新国家成立という過渡期に発生した東北軍残党 と、農民自衛団体の蜂起がある、このときは一部に経済的原因に政治変革と、反日的民族性が加わって、反満抗日を謳い、後に共産勢力台頭の萌芽となる。 ところが、烏賊、匪賊といってもいろいろある。土匪といわれる従来の職業的馬賊。半農半賊といわれた自衛団が、時には他村を襲えば馬賊になる。さらに宗教 匪という迷信的秘密結社のような集団馬賊。馬占山のように、抗日反満の政治匪。共匪といわれた共産党馬賊。鮮匪という朝鮮人馬賊。蒙匪という蒙古人馬賊と 雑多なもので、満州事変直後には、敗残兵を加えて、その数実に約三十六万に達したといわれている。しかも、満州事変によって治安が攪乱され、農業生産が徹 底的に破壊されたため、窮乏の結果匪賊化する農民が続出した。したがって、昭和七年の満州建国前後は最も治安も悪く、馬賊、匪賊が急増した時代であった。 満州建国後、関東軍は秋までに第一次東辺道地区、京奉、吉竜地区の諦討を行い、馬占山討伐、蕪病文のハイラル方面における叛乱、吉林省東部、遼河四角地 帯、安奉線三角地帯の掃討、錦州の張学良討伐と、いずれも関東軍は掃討作戦に東奔西走して、まさに寧日なき有様であった。しか も、特に手を焼いたのが、民衆の中に紛れこんだ匪賊で、連日のように小事件を発生させながら、正体をつかまえることがなかなか困難であった。それでも関東 軍や憲兵隊および警察は現行犯をよく捕え、捜査して犯人を検挙した。 こうして、建国以来、匪賊討伐の反復続行と、冶安活動は大量の逮捕者を出現させたが、これをいちいち繁雑な手続をして、悠長な公開裁判にかける時間的余裕 がなくなってしまった。犯罪者は後を絶たないからだ。しかも、裁判で事を長びかすことは、いたずらに民心に無用の動揺を与えることにもなる。この頃の満州 は中央を除けぱ、まだ、戦場だったのである。 さらにもう一つ。満州には古来から清郷委員会的な組織があって、県単位に簡易な裁判が行われていた。形式は米国の陪審員制度のようなものである。 大正十三年に長春憲兵分隊付であった鎌田光治上等兵(当時)の回想では、強盗、強姦、殺人犯人は重罪で、県の清郷委員会の裁判に付され、死刑が確定する と、県の公安隊が、犯人の背に処刑理由を書いた塔婆のような板を負わせ、街中を見せしめのため引回した後、刑場で犯人を立 たせて公安隊が銃殺にしていた。塔婆のような細長い板を背負っている犯人は、捧のように立ったまま処刑された。処刑のときは村や街の人々が総出で見物に来 る。したがって、凶悪犯人が処荊されるのは、当時の満州では当然なことであった。満州事変以前には、県の清郷委員会が裁判所らしい役目を果たしていた。 鎌田憲兵上等兵の回想では、長春の場合は通常、長春の西公園の野原で処刑が行われたが、その敷地が後に関東軍司令部となった。 事変以前の満州は、馬賊の頭領張作霖らが君臨して、治安対策が法的でなかったのは無理もないが、それでも、各地区にはたとえ形式だけでも裁判の真似事のよ うなものは存在していた。 それにもかかわらず、関東軍司令部は参謀長の名において、隷下憲兵隊に「厳重処分」という安易な処刑法を許可した。しかも、これが正式の通達となれば命令と同じ重みとなる。 これは参謀長の名において、関東軍司令部が隷下第一線部隊長に、厳重処分権ともいうべき資格を与えて、匪賊や敗残兵、また、反満抗日分子の現地処用を許し たことになる。これを憲兵隊が軍司今部の命令と解したのは当然のことだろう。そして、当時の関東軍司令部が、このような通諜を出さなければならなかった、 切迫した事情とは、新政府の基盤を危うくする組織的反抗と、個人的スバイ、テロなどの暗躍であった。 厳重処分とはある意味では、新政府の粛清工作の一部ともいえるのである。 関東軍司令部から「厳重処分」の通達が発せられた日時は明らかではないが、昭和七年 初頭のことといわれている。だが、これに対して、憲兵側から「厳重処分」の解釈について問いあわせが出ている。 それに応えたのが、次の通牒である。 昭和七年三月下旬、時の関東軍参謀長三宅光治少将は、隷下各部隊に次の通諜を発している。 「厳重処分とは、兵器を用うる議なり、と承知相成度し」 この通諜で隷下憲兵隊は「厳重処分」を即処刑と解釈して実行した。しかも、司令部はこれを黙認した形となって次第に普遍化していった。憲兵隊の「厳重処 分」は、こうして支郡事変および大東亜戦争下においても各地で実施さ れた。だが、現実には事に臨んで、「厳重処分」を実施しなかった慎重な憲兵も少くない。命令による場合を例外とすれば、「厳重処分」に反対の憲兵も多かっ たことを忘れては、片手落ちというものである。いずれにしても、「厳 重処分」が大変な悪習となった事実は否定できない。時代の進運は憲兵の「厳重処分」に、反省の機会を与える時問的余裕があったはずである。しかし、これが 戦場となると、再び憲兵の良心を麻痺させる何かがあったのである。実はそれが戦争というものなのである。 |
 トップページへもどる
トップページへもどる