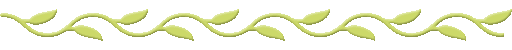
日本憲兵正史
不良在支邦人の悪徳行為
|
| 不良在支邦人の悪徳行為 | |
| 昭和十五年五月十八日、陸軍中央部は「対支処理方針」を決定した。その方針は、政、戦、謀略を統合強化して、昭和十五年末までに重慶
政権を屈伏させる・もし不成功の場合は、情勢の如何にかかわらず長期解決方策へ転換する、というものであった。 この頃、支那派遣軍は第十一軍をして、支那第五戦区軍主力を、漢口の西方にある揚子江の要衝宜昌付近に圧迫中であった。六月十二日、ついに宜昌を攻略し た。宜昌は航空機の重慶爆撃には絶好の中継地であった。こうして、日本陸海軍機の重慶爆撃は猛反復され、重慶政府内の抗戦、和平派の分裂が激化し、蒋介石 総統は最大の危機を迎えたのであった。 支那事変史を顧みると、この時期に堂々と寛大な条件で和平を求めたならば、事変の解決に成功したかも知れないといえる。 かって参謀本部作戦課の荒尾興功少佐は、南寧攻略時に次のように考えていた。「支那事変の解決は、武力をもって重慶、成都まで席捲するか、支那本土から撤 退するか二通りしかない。しかるに、大進攻作戦は対ソ戦備のため余力がなく、中央部の空気上望みがななかった。 当時、英国側の斡旋で、北支の一部と満州とを保持するだけで、他の占領地から撤退すれば、時局解決の見込みがあるとの判断もあったが、大陸に進出したわが経済力、政治力及び特殊権益の確保を切望する官民一体の権益 主義的世論の力は、軍の意志をもってしても、支那本土からの撤退はでき得ないものと統師部は考えていた。 従って、中途半端な施策ではあったが、補給路遮断作戦が、英仏対独戦に突入した機に乗じて企図された。北部仏印からの援蒋をことごとく遮断することが目的 だったが、仏国の情勢もそれほど熟していないので、中間目標として南寧を占領し、これを北部仏印への施策の跳越台にしようと考えられたのである」(「大本 営陸軍部」I) 以上の中で注目すべきことは、占領地に生れた特殊権益などの経済力、政治力である。特に事変下最も害をなした者が、支那大陸へ渡った傲慢な一旗組の邦人や利権屋であった。これらの人々は時勢に便乗し、軍の権威を 巧みに利用して、大都市繁華街の一角を不当に占め、その専横さは目に余るものがあった。これらは戦火を逃避した支那人の店舗などを、その留守中勝手に占有 し、持主が帰って来てもあれこれといいがかりをつけて返さない。しかも、多くは無料に等しい家賃を払って居直る始末であった。また、合弁会社なども名目の みで、多くは内地からの邦人が、その権利、利益を独占してはばからなかった。こういう輩に限って、直ぐ神社や思霊塔をつくりたがる。これらの人々の無神経 な思想が、どれほど支那民衆の反日感情を刺激したかわからない。このような連中が築 いた財産などは、権利でも何でもないのだが、さりとて軍が撤兵すれば財産を失い、支那民衆の報復を受けるのは必至である。軍は彼らを護って やらなければならない。軍の和平工作の妨害となったのは、まず、第一にこのような人々であったことを忘れてはならないだろう。 事実、総軍では、不良在支邦人の悪徳行為に苦慮して、その取締りを憲兵にもやらせているが、とても隅々までは及ばなかったのである。そして後の大東亜戦争 が避けられなかった原因の一つに、米国が要求した支那大陸からの全面撤兵がある。すると、支那へ渡ったいまわしき日本人の行為が、間接的に軍部に大東亜戦争への道を選ばせたものとい えないこともないだろう。もちろん、このことだけが開戦の原因ではないが、その責任は決して軽くはないのである。 |
 トップページへもどる
トップページへもどる