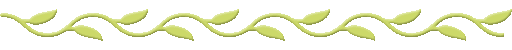
日本憲兵正史
夢幻泡影
|
| 夢幻泡影 | |
| .・・・この教訓が示すものは、いやしくも大東亜戦争の勝利によって、日本の指導者および軍人を戦争犯罪者として裁いた連合各国は、
いかなることがあっても、再び戦争を惹起してはならないということである。それでなけれぱ正義、人道の名において日本を裁いた意味が消滅するばかりか、国
家の正義が虚偽になるばかりでなく、自国の不正義を世界史の上に永久に刻みつけることになるからである。 また、戦争裁判の記録は、日本においても容易に公開されないだろう。被告の人権を尊重するというのが理由である。これも当然なことである。けれども、その 真の理由は、公開によって暴露された戦争裁判の実態が、いかに正義と人道に反するものであったかを示しているからである。公開されて困るのは、被告にあら ずして連合国側なのである。 (夢幻泡影) 戦後、民衆やマスコミから、戦前の憲兵の言動が非難されたのは、大きくわけて理由が三つある。 第一に憲兵の権限が非常に強力で、役目とはいえ戦時中に思想、言論の自由を弾圧した側にあったこと。 次に軍事警察が、軍法会議という非公開法廷で処理されたこと。これが民衆にとって恐怖の的になった。 最後が、戦犯者の中に憲兵が最も多かったこと。 これだけ条件が揃っては、憲兵が民衆に嫌われ、誤解されたのも当然であったろう。この中で憲兵のイメージを最もダウンさせたのが、戦犯という名の犯罪で あった。 戦争犯罪は国際法に違反した非人道的行為であり、このような行為を敢えてする者は人類の敵である、という形式的な論法が、現在もなお民衆の間に根強く扶植 されている。そして、戦争犯罪者、いわゆる戦犯者の烙印を最も多く押された兵種が、憲兵であったことから、戦後、憲兵に対する憎悪非難は、華々しいマスコ ミの批判に乗りて一挙に高潮した。 戦前の憲兵が特高警察とともに思想言論の弾圧的立場に立ったところから、軍国主義時代の権力の走狗として知識人から憎悪蔑視されたのは、その権力の大きさ を考慮すれば、これはやむを得ないことだろう。確かに憲兵にも非難されるべき過度の言動のあったことは否定できない。憲兵の上層部はもちろん上等兵に至る まで、軍人としてのエリート意識が強かった点も指摘されるだろう。けれども、軍隊が存立する以上、その軍紀を取締る機関が必要なのもまた論をまたない。 憲兵が軍事警察のみを、その職務としたならば、史上これほどの非難攻撃は受けなかったろう。しかし、現実には憲兵の職務は必要以上に拡大され利用された。 だが、それは多くの憲兵の意志ではなかった。 侵略戦争の責任を一般将兵に問わないのと同様に、憲兵隊の行動を憲兵個々の責任にのみ負わされるのも大きな誤りである。野戦憲兵が独自の判断で犯人を処用 したなどという例は極めて少ない。形式的には、すべて軍最高指揮官の命令によるものである。 けれども、現実の間題として、憲兵隊に命令を下達したのは殆ど軍幕僚であった。前述のように、時には幕僚部の二、三の参謀が正式の軍司令官命令を受けず、 勝手に軍命令と称して憲兵隊に実行させた場合もある。この場合参謀の指示はもう命令と同様な値値がある。先に示したシンガポールにおける華僑粛清事件にお いて、命令を本当と判断した憲兵隊長が、それを最高指揮官に訴えて取消させる勇気のなかったことは、憲兵側の責任として非難されてもやむを得ない。だが、 それが現実にできなかったところ に、日本軍の命令の峻厳さがあったのである。 さらに、もう一つ憲兵が不利な立場に立たされたものに、最高指揮官、つまり軍司令官の信念または態度の曖昧さがある。 憲兵隊長からの事件処蘆に関する上申に対して、 「そんなことを私に間くな」 「然るべく処置せよ」 などと応えるのは、明らかに責任回避ともいえる。 日本軍隊の悪弊の一つに「厳重処分」という言葉があった。 これは満州事変直後のきわめて治安状態の悪い、換言すれれぱ、戦争状態の中で、現行犯の兇悪犯人を捕えて処刑したことから生れた言葉である。この非人道的 行為は戦場であったことにもよるが、「事変は戦争にあらず。故に陸戦法規に従わなく ともよかろう」という考えや、相手が満州 の匪賊であったことにもよる。しかし、このような行為を黙認したかのような上司の態度は、やはり教育指導の誤りであろう。 しかし、現実は処刑ばかりしたわけではなく、匪賊に対する帰順工作などは前述のとおりである。また、協力を誓った者や生業につく者には、憲兵としての協力 指導もしている。だが、いくつかの正義も、一つの暴虐行為がもとで 雲霧となり、悪名を浴びなければならないのも世のつねである。この意味からも、満州で犯した憲兵隊上層部の指導的過誤は、支那事変から大東亜戦争下の憲兵 にも、再び大きな過誤を犯させる原因ともなっている。 職務に思実なことは、いずれの社会でも公正に評価されるべきである。しかし、これが人を取締る人間となると、徴妙な問題が生じてくる。法の解釈、運用は原 則があるが、やはりそれだけでは人間社会の秩序がスムーズにいか ないのは、昔も今も変わらない。そこに人を取調べ裁く側に、豊かな知識と人間性が要求される。 戦前の憲兵にとって、最も欠けた点が以上の点にあったことも認めないわけにはいかない。 軍隊の中の優秀者を憲兵とした軍の方針に誤りはないが、その教育に欠けるものがあったことも指摘できるだろう。 軍隊が人間社会の縮図であることはいうまでもないが、軍隊には一般社会とは全く異質な、厳然とした階級組織と軍紀があった。そして部下はいかなる理由が あっても、上官の命令に従うことが要求されただけに、特に指揮官の人格形成が重視された。人間が生命を賭けて人間を指揮統率するからには、上級者になるほ ど豊かな人間性が要求されたのである。 憲兵も同様であった。時には軍司令官以上の豊かな人間性を要求される場合もあったはずである。だが、これを憲兵全員に望むのは無理というものだろう。しか し、指揮官はそれでなけれぱならなかった。 戦後、天皇制が問題となり、現在もなお、多くの議論が巷間伝えられているが、少なくとも「軍人勅論」の精神は間違ってはいない。軍隊教育の誤りや、政治の 軍国主義化とは論理の次元を異にする問題であって、「教育勅語」と ともに、その精神的本義まで悪としてはならないだろう。いずれの国家においても、軍隊そのものが好ましい存在であるはずはないが、現在もなお世界列強が軍 備をゆるがせにしないのは、国境を越えた共通性があるからだ。軍隊のあるところ、必ず軍事警察的存在もまた否定できない。 そして、かつての日本軍隊も、列強同様に存在理由があり、憲兵もそうであった。だが、憲兵の精神も人間性も使命も、求められるものは過大崇高であり、憲兵 個人その重みを背負いきれなかった。憲兵もまた凡人の域を脱し得なかったからである。 戦後、約三十年の歴史の上で、これまで憲兵が解放された日は一日もなかったといえる。それは日本近代史上、憲兵の位置するところがなかったからであろう。 これまで多くの元憲兵が強靱な重い沈黙の中に、世の非難罵声に耐えてきたのも、敗戦とともに元憲兵のうえに吹き始めた冷い風の中で、軍人として歩いた棘の 遣を、反省として噛み占めていたからである。さらに多くの憲兵がたどった戦争遂行の人生の軌跡は、大東亜戦争で敗戦という辛酸をなめた、数千万民衆の遅命 にかかわってくる。 (憲友会の創立) 昭和二十年八月十五日、日本は大東亜戦争に敗れた。文字どおり国破れて山河ありと、史上未曽有の国難を経験したのであった。それから三十一年の歳月が過ぎ た。月日のたつのは早いものである。この間、われわれは思いもよらぬ平和と繁栄を講歌してきた。そして、それがまるで日本人自身の手で築き上げたような、 錯覚さえもっている人々が多い。実は、複雑な国際政冶の徴妙なパランスの上に立っ て、しかも、多分な幸逼に恵まれたものであった。 だが、これからの日本民族の命逼は、所詮人智ではかり得ない。それは天命だからである。だからこそ、われわれは人事を尽して天 命を待つよりはかはない。その人事が、宇宙の真理や自然の摂理を求めて、一世紀に満たない人生をおくりながら、民族の平和と繁栄を、次代の子に引継ぐ努力 である。われわれは天命には絶対に勝てない。また、逆えない。 ここに宗教の存在価値があるが、国家の存立は、宗教だけでは得られないところに、民族の治乱興亡がみられる。政治の要諦は先見的洞察力にある。いわゆる先 見の明である。 けれども、残念ながら現代の日本にはそれがみられない。世遣人心日に非なる現在、この国は亡国の一途をたどるのではないか、という危惧が脳裡からついて離 れないのも、政治に先立つ教育の腐敗による。戦前の精神主義を非難するあまり、かつての東洋的哲学、美しき伝統まで見失ってしまったこの国に、輝かしい、 そして精神的に豊かな社会は、もう当分は戻らないだろう。 |
 トップページへもどる
トップページへもどる