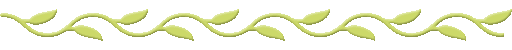
安全神話崩壊のパラドックス
|
 |
| コ メント | |
カバーにしっかりと「著者は統計資料の徹底的な読みこみをとおしてわが国の犯罪状況を分析し、近年の通説が現実を正しく反映していないことを考証。なぜそのような言説が一般的にまかりとおるのことんびなった のか、その背景と言説自体がもつ意味を明らかにした上で、欧米社会との比較を加えつ つ、今後の社会変化と法状況の将来を展望する。 法とは何かを問うことを通して、わが国における司法制度や社会関係のあるべき姿について考察した・・・」とある。 ・・・素人市民に犯罪状況を説明する困難は、素人の実感と統計的事実がスレているからである。そして、このズレの原因こそ、究明の価値があると考えられ る。最も単純には、現在の治安悪化が間違って信じられている以上に、過去が安全であったのがウソだったのが原因ではないかと考える。 ・・・焦点は、治安維持の伝統仕組みの揺らぎである。 治安維持の伝統仕組みは、、むろん安全神話と連携してきた。その重要な特徴のひとつは、その仕組みが隠蔽されてきたことである。もっと明確に言うなら、隠 蔽した形でしか機能しない仕組みであった。そして、うまくいっているから(これ自体が安全神話だが)という理由で治安関係の情報開示は極端なほど控えられ てきたと考える。この考えに立てば、この治安維持の伝統的な仕組みと安全神話のメカニズムを明らかにすることは、そのメカニズムを葬り去ることを結果的に 引き起こす。私は、そのことを十分に自覚した上で、それを実行し、将来のあるべき社会像に結び付けたいと考えている。これが本書の中心的狙いである。 基本モデル オオカミとウサギの共同体。 オオカミとウサギが同一地域に共存するといえば、そもそもその比喩を借りてきた自然界において、実はあたりまえに実現している・・・両者とも同一地域に存 続するのは、オオカミとウサギが出会わないからである。・・・避けつづけることによる衝突回避、つまり秩序維持をはかるモデルもありうるわけである。 人間社会にあって、構成員が避けたがっているような集団を共同体と呼ばないというのも1つの考えであろうが、社会的、文化的境界によってお付き合いを限定 することは、よく観察されることであろう。私は本書で、この境界の機能にとりわけ注目したい。犯罪の世界でがは境界がはたす役割はきわめて重要であると私 は考えている。 ・・・ (繁華街vs郊外の住宅街)街の境界の弱体化によって犯罪の危険にさらされる可能性が増大する、あるいは心理的に守られている感覚を喪失するようになって いると考えられる。 守られているという感覚とは、境界によって区切られて、ある囲いのなかにいると感じることと、ほぼ同義であろう。 日本の安全神話について、この守られたウサギたちのモデルを使って説明したい・・・ (防犯力の衰退) 軽微な犯罪の更正と・マージナルマン・身元引受人の能力、世話好きの減少〜 業界頼みの防犯力の低下・質店(盗品)、ガソリンスタンド(交通事故、ひき逃げ)など、また犯罪者の社会復帰の受け皿としての業界など、弱体化が目だって いる。 (エリートと共同体) このように考えるならば、共同体として最も問題なのはいわゆつ郊外ニュータウンであろう、、、有名な突飛な犯罪事件の多くはニュータウンで起きている。赤 坂憲雄は、いじめについて強いものが弱いものをいじめるのでなくて、同質社会で、誰もが自分がいじめの対象になるかもしれない状況において、その怖さか らいじめが発生しており、ニュータウンはその典型例としている。 警察,検察、裁判所、矯正、保護、いずれの分野であれ、その幹部が犯罪者がどのような人々なのか理解している必要がある。さまざまな観点からかけているも のがある。不幸で不運な人々のことを理解していなくて、幹部がその責務を果たすことができるはずがない、、、個人を完成させるという視点からいっても、全 てを含んだとまでいかずとも、大きな多様性を含んだ共同体が不可欠なのである。 (要求の高い住民ー「自由」な人々) 変化の中心をなすのは、人々を拘束してきた伝統的共同体の衰退、それっもとりわけ匿名社会化であったことである。匿名化は差別を解消に向かわせた。そし て、この差別こそ、犯罪者を一般住民から隔離するという排除を行ないながら、社会全体から追放しないで再統合する方法の環であった。 共同体から「自由」になった人々はミニコミを失い、マスコミに頼る。その結果、犯罪情報のマスコミを通じての公開が要求される。彼らは好きな時間に、どこ にでも出かけて、その上で安全を要求する。合理的な判断ができる責任が持てる個人ならば、完全な安全など実現できるはずはなく、しかも要求するだけでな く、自分たちが協力することを考えねばならない。安全神話に守られなくなった後にうまれたのは、不安に耐えられない個人とも市民とも呼べない「要求の高い 住民」であった。 正しい情報公開を求めるならば、公的機関の無謬神話は捨てなければならないし、犯罪行為あるいは犯罪者との共存を受容しなければならない。犯罪学者とマス コミが協力し合って、一般向けに啓蒙あるいは説明することが必要である。 ・・・厳罰を排し、赦しを与え、ひとりひとりを個別に丁寧に扱う、よき伝統の継承が危ぶまれていると感じるところもある。たとえば、近年量刑は二倍になっ たし、少年事件の簡易送致が拡大している。表面上の法制度ではなく、私が本書で記述した、日本の治安政策の「知恵」について,よく理解していない刑事司法 職員が、少なからず存在するように思える。この知恵について、それが失いかけている今、継承すべきところとそうでないところを論じる必要があると考えたこ とも本書執筆の動機であった。安全神話は捨てるほかないが、良き伝統は残すべきである。 (蛇足) 治安の悪化が叫ばれる現在、それだけでなく、日本中をペシミズムが被っているように感じられる。 これは視点を変えると、何かペシミズムを醸し出したい者が、そのネタに治安問題を使っていると考えられないであろうか。 賃下げするために、みなを納得させるためにペシミズムが必要とされており、治安問題はその雰囲気作りに使われてているという仮説が提出できる。乱暴過ぎる 議論であるが、治安問題を、さらに大きペシミズム問題との関連を意識して捉えることは必要であろう。 本書の100ページほどは、数値の分析という興味のある構成となっている。検挙率、犯罪者比率、認知件数、発生率などである。本書で最も需要なものは、こ の数値にある。 都心周辺の代議士の政治主張に頻繁に取り上げられている「治安不安」が、このようなもの数字上に形成されたもある。地域での犯罪統計が公表されている時 代、新宿、渋谷などの旧来の繁華街でのシステムと都心周辺でのシステムを別のものとして理解することは難しくないであろう。 |
 トップページへもどる
トップページへもどる