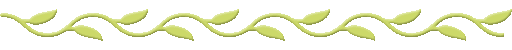
2003年2月のメモ
| 公共サービスとデジタルデバイド | |
|
公共サービスの分野の「倫理・法令」では、個人情報保護対策の厳密な運用が要求される社会となっています。憲法「通信の自由」への公務員としての義務が明記され、違反については刑事罰まで法制化されている郵政職員の立場が、今後の法制、基準に参考となるでしょう。急速な情報社会の進展による問題発生は増大し、対策は深刻なものになっていきます。しかし、強調したいのは、「図書館の自由に関する宣言」のベースとなっている「基本的市民権利」という志向です。 ネット社会の加速で「デジタル・デバイド」(情報格差)が問題となっています。サービス、情報提供、呼びかけなど、低コストで瞬時に多数者に伝えるメディアとして、商業、民間利用だけでなく法人、官庁の情報公開・説明責任にまで利用されているからです。 文化、教育、趣味などひとりの市民として<発信>するケースも多く、さらに草の根団体、市民グループとして、ネット上での情報の<共有>を通じ、新しい形のコミュニケーションのスタイルも生まれています。実際にネットで流れる情報サービスから取り残され<受信>できない人々の不利益の拡大は、解決を迫られる社会問題になりつつあります。 しかし、一般に思われている「デジタル・デバイド」問題の解消は、決して<受信>レベルでの解決だけではありません。高額な資金を投入できる企業やメディア産業や、ネット販売や有料サービスなどへの勧誘を図るネットビジネスの、動画やJAVAを利用した華麗なホームページが、市民の人気を得ている実情があります。さらに、誤情報や面白半分の意図的な悪質情報が、匿名性の強いネット上で流れています。誰でも<受信>し、<発信>し、情報に<参加>するメディアとしてのインターネットで、現実には「悪貨が良貨を駆逐し」「良書が埋もれる」状態が見聞できます。 インターネットの健全な発達を保障していく「良書を掘り出す」「良書を作り出す」視点が必要です。この街にも、急激な都市化問題、福祉、リサイクルなど、市民の良識ある提案、地域に根ざし自立した市民グループ、経験、資料、書誌が多くあります。これらの新しいメディアへの<発信><共有><参加>まで教育、技術面でサポートすることが、ネット社会の多元的な発達を保障する、(デジタル・デバイドを<受信>対策だけにしない)トータルな対策として必要だと思われます。これはデジタル社会の問題意識ですが、公共図書館が書籍・書誌の情報格差に基本的市民権利として成立、発展してきた経緯と重ねあわせることもできるでしょう。 また、IT専門技術者の活用する場を広げることにもなります。主役は市民です。しかし、研究者の現在の常識となっている情報検索を可能とする資料・書誌のデータベース化への情報投資、教育、研修など、IT専門技術者の技能の発揮する専門分野があります。また、情報公開の必要性に迫られながら遅れている自治体の資料の散逸を防ぐことも必要です。「公共図書館」の充実したサービスは無理だとしても、所蔵資料、書誌目録の公開だけも、わたしたちは地域の多元的な文化、情報の豊かさを全国に発信できます。また、情報公開の必要性に迫られながら遅れている自治体の資料の散逸を防ぐことも同様です。 「遺伝子戦争」という言葉があります。多くの世界的企業が有用な細菌、遺伝子を求め、アマゾンやアフリカに調査隊を派遣しています。稀少な遺伝子をバイオ技術で特許化するとのことです。私たちの町の埋もれた情報は、特許、独占するものではありませんが、貴重な市民の経験です。わたしたちは, この町の多元的な文化、情報の豊かさを全国に発信、共有し、風聞や流行に追われない地域の体験を基礎とした価値観の形成による<市民参加>も、基本的な市民的権利と考えるべきでしょう。
。 |
 トップページへもどる
トップページへもどる