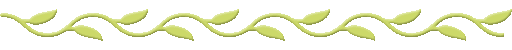
産業財マーケティング
|
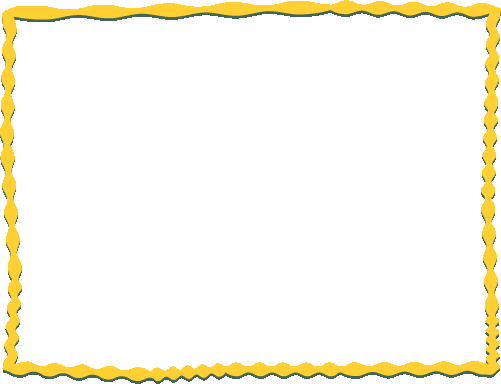
|
| コメント | |
| [護送船団」「系列」という実態で見ると、この産業財ビジネス、さらに、そのコンサルタントなど成立しえない。「生殺与奪権」をもったクライアントに「精度、納期、物流」さらに「企業風土、企業文化の共有」「運命共同体、血縁」でつながっている。 しかし、かつてのように、相手方企業自体が生き残りをかけ、グローバルに調達し、基幹部門をリストラし、外注し、メガ・ビジネスにボーダーレス化していくとく、「「営業」マーケティングの可能性はどこにあるのだろう。 この不況下、新規ビジネスは参入時判断に迷い、市場の成長を待てずに撤退するか、先行社の業績を横目で見るか?アイデアや技術は優れても、一過性のものに終わるか? しかし、この不明な時代に、産業財社としては、相手方企業の開発、製造、さらに企画部門まで踏み入って共通のパートナーとして評価されるまで「営業」マーケティングを進めるしかない、とすれば、新しい手法の開発が、自社のコンテンツ(コア・ビジネス)の再確立、社内の人材、社外に培ったネットワークの創造にかかってくる、となる。 ここまでは、一般論。 必要なことは、e-ビジネスの進展下、顧客サービスの進化への悩みが消費財マーケットでも深刻下している。その意味で、常に「顧客の顔が見える」「高品質」「購入先との関係の深さ」が要求され、技術情報、市場情報から「徹底したアフターサービス」が義務である。 さらにポイントとして、絶対的なプロの顧客の「合理的、純経済的、かつ一方的」購入様式への営業活動が、注目され、研究されるべきである。 なぜなら、ますます一般消費者市場でも、個々の商品の市場規模は小さくなり、さらにニッチな競合が基本になっている。しかし、その狭い市場であっても、「定評」と「信頼」、さらに「勝ち組」と称されるブランドを作り上げる開発力が、生き残りの基本だからである。 ご存知のように、その市場の数%の高感度ユーザーを捕まえる基本であるからである。 さらに、労働問題として 旭ダイヤモンド工業を「成績不良」として1999/4/8解雇された営業部員伊藤和行氏の場合、地裁で解雇有効の判決となった。 高裁では、会社側の陳述(伊藤さんが「ユーザーへの対応が悪く、これが営業成績不良」との会社主張)を覆す「新証拠」が提出された。 これは、伊藤さんがユーザーを訪問し、「営業の対応に問題はなかった」「よくやっていた」との書面を集めたものである。 (これが、どれだけ大変なものか、裁判官にはわからない!) しかし、高裁の新村正人裁判長は証人尋問を開くことなく、地裁不当判決を追認。2002/6/28には最高裁でも確定した。 しかし、伊藤さんのような、価格決定権や技術的蓄積もない「産業財営業」の場合、何を基準に成績を判断するのか? 業界を知っている人間なら誰でもわかるウソを見抜けないのが、裁判官であることを如実にあらわす判決である。 裁判所関係者にとっての営業とは、飲み屋やパーティー、ゴルフといった世界である。 一般社会でも、自宅に直接訪れる「外まわりの営業」とは、新聞の勧誘と宗教団体である。 職場への営業は?保険勧誘? 個々の業界で育てられる「産業財営業」の場合、裁判所は理解できないのが、伊藤氏への不当判決の背景にある。 |
 トップページへもどる
トップページへもどる