|
|
|
|
|
|
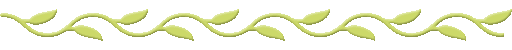
| 某月某日 ZAKZAK 2007/11 鳩山邦夫法相が31日の衆院法務委員会で、田中角栄元首相の私設秘書時代、米国防総省(ペンタゴン)から、毎月のように接待を受けていたことを明らかにした。事実上、米国の情報収集の協力者(スパイ)だったことを認めたもので、先日の「友人の友人はアル・カイーダ」発言と合わせて、大臣としての資質が問われそうだ。
衝撃発言は、民主党の河村たかし議員の質問中に飛び出した。河村氏が日本の情報収集について質問していたところ、鳩山氏は指名もされていないのに突然、「委員長!」と手を挙げて立ち上がり、河村氏が「大臣、何ですか?」と驚いている間に、こう語り始めたのだ。
「思い出を話させてほしい。私が田中角栄先生の私設秘書になったとき、毎月のように、ペンタゴンがやってきて食事をごちそうしてくれた。当時、私は金がありませんから『ウナギが良い』とか『天ぷらだ』などと言ってた。私は1円も払っていない」・・・政治評論家の森田実氏は「欧米では即刻更迭される発言だ。鳩山氏自ら職を辞するか、福田康夫首相が更迭すべきだ。これを放置すれば、日本政府に対する国内外の信用を失墜しかねない。先日の『私の友人の友人はアル・カイーダ』という発言もそうだが、鳩山氏は常軌を逸している。法相のような要職に就けるべき人間ではない」と語っている。 |
| 某月某日 ゼロ円生活って何?と聞かれて、ジャガイモと玉ねぎ、ニンジンのブイヨン煮の話をした。
これだけでも、なかなかにおいしいものである。ただ、この国は、主食でないせいか?北海道の特産品となってしまって、価格が独占状態か?ジャガイモもタマネギもバターと同じように高額品となっているのが残念。 さて、ひとり暮らしなら、必ず「あまるように作る」(一回こっきりにするには、コンビニ・スーパーでの「高額な一人用」を購入するという酷いことになる。 一般的に「お一人様」価格は、家庭で作るならば、五人前以上の価格である。 翌日は、これに「カレー」を入れるか? 翌翌日は、肉類を増やして「肉じゃが」にするか? さらに、その「じゃがいも」だけ取り出して「コロッケ」にするか? どのように使いまわしても、同じように思えるかもしれないが、最初は「薄い色」が良い!色はあとから、どのようにでもつけられる。ケチャップだってある! 「じゃがいも」七変化と呼ぶ |
| 某月某日 公開処刑の衝撃
公開処刑というのは衝撃的なものである。市中引き回しの上に、鈴が森、千住、四条河原の処刑場へ連れていかれる。 魯訊の「阿Q正伝」も同様な世界である。 今回の千葉景子法相=法務官僚の「お立会い」の意味が、どのように「死刑廃止=世界の流れ」に 波紋を伝えていくのか? 「世界の流れ」に、追いつめられた「国家意思」の「悪あがき」と考えるのが正当な歴史的評価であろう かつての「法相=死神」キャンペーンで朝日新聞を叩いたことが、ジャーナリズムにトラウマとなり、逆に法務官僚の歪んだエネルギーになったことも想像できる。「被害者集団」が「首切り役人」千葉景子法相=法務官僚を崇拝することもあるだろう。しかし、司法は「現実の暴力装置」である。 矛盾のあるにも関わらす、「第二、第三の死神舌禍」を怖がって、報道と論議が押さえ込まれたことが大きい 今回の解放運動と国家公安担当相は、第二ラウンドとなる。 |
| 某月某日 港町、旅のよいとこ
河口の漁港の旅である。小さな町であるが、山林・田畑の風景から。、家並みが並ぶ光景に出くわすと、なんとなく知った街かのように感じられて不思議である。 友人から「(この街)絶対、気にいると思いますよ」「(温泉センターは)歩いていけるし、帰りは港を回ってくると良いですよ」と誘われ、ご入浴。 漁港への道すがら、看板も大きく「トルマリン風呂」、レトロであふれる生活感を満喫。蒸気が十分には上がらないサウナ、海水をひいた珍しい「潮湯」もある。男湯には私たちのほかには数人の客が入ってきた程度だが、聞こえてくる声から女湯は客が入っているようだ。 湯上りのビン牛乳の正しい飲み方とて、みな一緒になって、腰に片手を当てて飲み干したことも忘れられない。視線を上に向けるのもポイントらしい、実にうまい。 湯上りは漁港へ。小さな漁港ではない。遠くまで岸壁や倉庫、漁船が並んでいる。雨は上がったが厚い灰色の雲の空、防波堤沿いに歩くと、漁船のそれぞれに黄色い旗が飾ってある。海の労働安全運動?漁業協同組合の旗?近寄ってみると、黄色い旗の中央には、丸で囲った(金)の一文字、下段には「大漁満足!金比羅宮」、海の神様、金比羅さんの旗であった。国東半島の向こうは四国、讃岐・金比羅様は船でも行ける距離かと思うと、改めて九州にいる実感が迫ってきた。海を見ながら、叫ぶ者あり、黙る者あり、座る者あり、静かに波が打ち寄せる漁港の堰堤であった。 漁港へ続く県道と一部を除くと狭い路地の街である、車一台がやっとの道幅に東京では想像も出来ない太い用材と伝統の造作の伝統建築、立派な瓦をのせた組み木の屋根が並んでいる。入り込んだ路地のさきには、狭い敷地に似合わない巨樹に守られた粟島神社、海の神様の末社には大砲の砲弾まで飾られていた。 途中で「酒造場まで酒を仕入れにいきましょう」と誘われて路地に入りこむ。駐車場脇から、すこし歩いて、レンガ積みの煙突と黒壁が並びに、気持ちも酔わされてしまう。お話では、創業二百年を越え、日本酒も醸していたとのこと。帰りは高橋酒店、高橋醤油醸造場(いずれも立派なお屋敷)の横を戻ると駐車していた場所にでた。 「偶然、見つけたんです」とのことだが、歩けば酒蔵に当たる街がザラにあるものか!不思議な街である。コンビニや商店街、居酒屋はないようであるが、温泉センターへ行く途中に「とよきん醤油」もあった。製麺場も並んでいる。商家の裏の納屋のような「工場」から麺を打つモーターの音がゴトンゴトンと聞こえてきた。 漁港の「朝市」や海産物問屋もあるらしい、ネットで探せば、酒造所、醤油醸造、製麺所が多数、この路地のなかにあるとのこと。環境の変化による漁獲高の激減が、この漁港・地域の衰退をもたらしてきたとの説明もあった。それでもこれだけの伝統産業が息ついており、思わぬ感動をもたらしてくれたのであった。 「知らない街を歩いてみたい」とは旅のロマンであるが、海外ですら驚くことが少なくなってしまった現在、手仕事時代の歴史と文化を丸ごと残している路地というのは、褒めすぎであろうか? しかし、こんな街だ、きっと頑迷にゴチゴチに保守的なんだろうな!(S) |