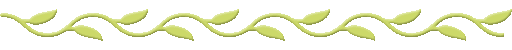
 ���_�ʑ� �̖@�������@�ρ@���F�@�O����2005 �����ٌ�m��@�l���i��ψ���/���٘A�@�l���ƕɊւ��钲�������ψ��� ���_�ʑ��ٔ��A�v���C�o�V�[�N�Q�ٔ��ւ̍��z�������������s���鎞��i�u�\�̐^���v�̒⊧���R�̂ЂƂɂȂ��Ă��܂������j�ɂ����āA�����Ƃ̑����瑽�� �̔��ᕪ�͂����p���ڍׂɉ���B �Ɛӎ��R��^�����E�^���������̍R�قƗ��ؐӔC �u���_�ʑ��̖Ɛӎ��R���l����ꍇ�A��͂薼�_�ʑ��@���������ێ��̋@�\��L���Ă����Ƃ������j�I�w�i�܂����ɂ͂����Ȃ��B�����ɖ��_�ʑ��ɂ����� ���Ƃ����I�Ȍ��_�͐�ɐ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���A�Ɛӎ��R�͂�������I���_�̎��R��ۏႷ����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B �u�z���g�̂��Ƃ����炢���Ă�������Ȃ����H�v �u�z���g���Ǝv���Ă��܂����̂�����d���Ȃ�����Ȃ����v ���I���_�̎��R��ۏႷ�邽�߂ɂ́A�L���Ɛӂ�^����K�v�����邪�A������ϓ_���猾���ƁA���݂̐^����,�^���������̍R�ق��\���̎��R��ۏႵ�Ă���� �����邩�͂��Ȃ�^��ł���B ���ɐ^����,�^���������̍R�ق̎咣���ؐӔC����ɕ\���ґ��������Ƃ����_�͕\���ҁi���f�B�A�j�ɉߏd�ȕ��S�ł���Ƃ����悤�B �L���ɏ����ꂽ���́A�����ꂽ�L���̎������b1���Ƃ��ď؋���o���đ����A���Ƃ͕\���ҁi���f�B�A�j���ŋL���̐^�������𗧏���̂�҂��Ă���� ���킯�ł���A�����ꂽ���͒�i���邾���Ń��f�B�A�ɑ��\���ȃv���b�V���[��^���邱�Ƃ��ł���̂ł���B���悤�ȕ��S���l���ă��f�B�A�����l�Ɋւ��� �Ɉޏk���邱�Ƃ����͋����B ��1���@���_�ʑ��̐����v�� ��1�́@�T�_�@ ��2�́@�e�_�ʁi�}�́A�����A���N�����A���f�������@���3�́@���Q�_ ��4�́@�u���Q�v�A�����A���K�ȊO�̋~�ώ�i ��2���@���_�ʑ��̖Ɛӗv�� ��1�́@�^����,�^���������̖@���u�����̗��Q�Ɋւ��鎖���v�̈Ӗ��A�ړI�̌��v���A�u���l�v�A�^�����A���ؐӔC�̓]�� ��2�́@�z�M�T�[�r�X ��3�́@�����Ș_�]�̖@�� ��4�́@�����̈��ӂ̖@�� ��5�́@���_�̉��V�̏ꍇ�̖Ɛӂ̖@�� ��6�́@�����Ɩ��s�� ��7�́@��Q�҂̏��� ��3���@���_�ʑ��̔�Q��Ɋւ��鏔��� ��1�́@��Q ��2�́@��Q�~�ς̂��߂̊e��� �Ⴆ�A�ٌ�m�Ɩ��Ɋւ��鎖���Ƃ��� �ٌ�m�́u�˗��҂ɈϔC���ꂽ�@�����e�������Ǒ��ɔ�����Ȃǖ����Ɉ�@�ȏꍇ�A���邢�͈˗����e�̎�������@�Ȍ��ʂ��������邱�Ƃɂ��ٌ�m�����ӂ� ���͏d�ߎ��ł������ꍇ����O�I�ȏꍇ�������A�˗��҂̈˗��ōs�Ȃ����s�ׂ́A�����Ɩ��s�ׂƂ��Ĉ�@�����j�p�������̂Ɖ�����̂������ł���v ���̂����ŁA���_�ʑ��s�ׂɂ��Ă��u���ɁA�ٌ�m�̋Ɩ��̐�����A�˗��҂Ɨ��Q�̑Η����闧��ɂ�����̖̂��_,�M�p�ɒ�G���邱�ƂɂȂ�ꍇ�͂����� ���Ȃ��̂ł���A������ꍇ�ł��ٌ�m�Ƃ��Ă̂��̔C����s�����K�v������̂͂����܂ł��Ȃ��v�u�ʒm�̕K�v�������������ƕ��тɒʒm�̓��e�A��i�y�ѕ� �@�������Ȃ��̂ł���ƔF�߂���Ƃ��́A�����Ɩ��s�א�������Ȃ��v�����n��1993�����1492���B �i�ׂɂ�����ٌ�m�٘̕_�ł� ���R�A�u�i�ׂɂ����Ă͕٘_��`�E�����Ҏ�`����{�Ƃ��閯���i�ׂł͒������s�K�ȕ\�����e�A���@�A�ԗl�ő�����̖��_���Q����ꍇ�́A�Љ�I�ɋ��e�� ���͈͂���E���Ȃ������@���j�p����������v�̂ł��邩��A���̏ꍇ�A�퍐�����R�قƂ��ĖƐӎ��R���咣������̂łȂ��A ���_�ʑ����咣���錴�������u�u�������s�K�ȕ\�����e�A���@�A�ԗl�ő�����̖��_���Q���邱�Ƃ��Ӑ}���A���U�̎����܂��͓��Y�����ƊW�̖����������� �����A�܂��͈Ӑ}���Ȃ��Ă��A�����̍����̖������Ƃ��A�Љ�I�ɋ��e�����͈͂���E���A�i�א��s��̕K�v���������Ď咣�����v���Ƃ��咣������Ȃ��� �Ȃ�Ȃ����ƂƂȂ��Ă���B �����I���_�̕ی� �|�c���u���_��v���C�o�V�[�E��Ɣ閧�N�Q�̖@�������v1976�ł͋����ی�̕K�v���ɂ��� �u�����ł���Ƃ��Ă����_���ے肳���Ȃ�A������铖�l�̐����ɑ傫�ȉe����^���邾���łȂ��A�Љ�S�ʂɓ��l�������炷�댯������v�Ƃ��u�@�̎Љ� �����ێ��̋@�\�v�̏��Y�Ƃ���B �������A���_�ʑ����ւ���Ƃ����V�X�e���͂��Ƃ���,�l�̐l�i���̕ی�Ƃ����ϓ_�ł͂Ȃ��A�Љ���ێ��̊ϓ_����݂���ꂽ���̂ł���A���l�����l �ɑ��閼�_�ʑ����d���ֈ����邱�ƂŌ��͔ᔻ���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă������Ƃł���B �����炱�����_�����@���̉��ߓK�p�͔����œ���̂ł��� �u���_�̕ی�v�u�������l�̕ی�v���A�������l���Ă���ƁA���̐�ɑ҂��Ă���̂�,���ɂ������Ȃ��A���������Ȃ�,�����ᔻ�ł��Ȃ����̒��ł� ��B ���� �ٔ���A������B �@�����W�͂��炵���Ȃ����A�Z�N�n���̉ߋ�������B�������A����͑i�����邱�Ƃ��Ȃ��A�����Ă����{�l���L���������B �A�u�������������v���Ƃ���ꂽ���Ƃ�����B �B�����̈ړ��ł͊�������̂�����B �C�^�Ђ̊���X���^���ꂽ�B ���̂悤�ȗ�̏ꍇ�A���̒ቺ�����_�ʑ��ɂ�����̂ł��낤���H �����I���_�A�O���I���_�i�Љ�I�]���j�A���_����i��ϓI���_�j����ɋ����I���_�́u�i�s�A���s�A�����A�M�p�Ȃǂ̐l�i�I���l�ɂ��ĎЉ���q�� �I�]������@�ɐN�Q���邱�Ɓv�ƒ�`�����B��̓I�ɂ͎Љ�I�]���̒ቺ���܂˂��������ł���B �������A �����I�ɂ́A�Љ�I�]�����̂���������̂��H�Ƃ�������I�Ȗ�肪����B ����Ƀv���C�o�V�[����u�h���Ǖ�̏�v�u����Ȃ������v�ȂǁA�������čٔ��������_�ʑ��Ƃ��Ă��邱�Ƃ́A�s������������낤�Ƃ�����̂ŁA���̍� �̌���������ɈӋ`�[���B �Y�@��ł� �Y�@��ł́u������K��������́v�����_�ʑ��߂ł���A�u�����K���v�̂Ȃ����̂����J�߂ɂȂ�B ���J�߂͖@�l�ւ̕��J�ɂ��K�p����Ă���A���_�����ی�@�v�ɂ�����̂łȂ��O���I���_�ƍl����ׂ��ł���B ���̏�ŁA�Y�@��ɂ����Ă��u�̈Ӂv�u�ߎ��v�̕ʂȂ��A�u�i���Ƃ���M�Ƃ��Ă��j�m���Ȏ����A�����ɏƂ炵�A�����ȗ��R����ꍇ�v�̂ݖƐӂ����B �\���̎��R�̏d�v���Ɋӂ݂�Ƃ��A���̂悤�Ɍ̈ӂ܂��͉ߎ��ɂ��s�ׂ܂ŏ������邱�Ƃ͑Ó��ł��낤���B���Ƃ������{������Y������w�i�Ɍ��_�̐ӔC�� �Njy����Ƃ��������Ԃ�,�\���̎��R�ɑ��邱��ȏ�Ȃ��قǂ̋��Ђł���B�܂��đΏۂ͌��I���_�Ȃ̂ł���B�v���I���_�̎��R���y�I�ɕۏႷ��Ƃ��� �ϓ_���炷��ƁA�O�L�ō��ق̖Ɛӗv���͌���������Ƃ��킴������Ȃ��B����čl����Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł���Ǝ��͎v���B |
���w�L�^�ɂ��d���������I
|
| ��
�����p�فE��g���X�u�n�����̃p�m���}�v�Q�O�O�S ��g���X�̎G���n�����R���N�V�����Q�X�O�O�������P�T�O�O���̕\���́u���o�I���́v���A���s�N�x���ɂȂ�ׂ���E�E�E �������p�فu�n�����̃p�m���}�`�ߑ���{�̎G���E��g���X�R���N�V�������v�W�Q�O�O�S�̃J�^���O�߂Ă���B�Q�X�O�O���̌c���R�N�P�W�U�V�N����s ���P�X�T�P�N�܂ł́u�n�����v�𒆐S�ɂ������u�Óc�E�^�����Óc���X�E�_�c��_�ے��V�v�R���N�V�����́A�P�X�T�O�N��Ɋ�g���X�ɏ�������Ă����B ���p�W�}�^�Ɂu�N���b�N�I�v������Ύ����Ɋg�傷��̂ł͂Ȃ����Ƃ���ɁA�����T�C�Y�ŕ\�����N�㏇�ɕ��ׂ��Ă���B �������A���X�ł̕��ςݏ�ԂƂ͈���Đ}�^�ɂ͕��ׂ��Ă���B�G���̎��T�C�Y�͂`�S�C�a�T�ƌ��܂��Ă���킯�ł��Ȃ��̂����A�J�^���O��ɂ͊g�奏k�� ���ē��T�C�Y�ɂȂ����G���̂P�W�O�s�N�Z��X�P�Q�O�s�N�Z�����炢�̃U���l�C�������ׂ��Ă���B �i�����T �C�Y�́A�����̎G���������ɏo�Ă���j �i����͊�Ȋ��o�ł���j �����ȏ��X�ł��A�G���́u�j�����v�u�������v�u�X�|�[�c�v�u�r�W�l�X�v�ȂǕ��ނ���A���ς݂����łȂ��I�ɕ��ׂ��邱�Ƃŋ�ʂ�����̂����A�W������ ��o�Ő��̑召���킸�A�\�������̃R���N�V�������N��ʂɕ��ׂ��Ă���̂ł���B ���ނ��Ȃ��A���s������G���̕]������킸�ɕ��ׂ�̂�����A���݂ł͏��X�ɂ͂Ȃ��w��⓯�l���A�L�A�����E�@�����Ў��Ȃǂ�����ƂȂ��Ă���B �u�ׂ�ނ�ׁv����������/�\���F�����K1905�͘r�܂���̍]�˂��q�̕\���Ȃ̂ŕ��͋C�͓`��邪�A�]�ˎ�̎G�����ǂ����H �u�ىԎ�فv���E�ىԎ�ٔ��s��1913�́A�E���ɏ������k�[�h���������Ă��邪�A�Ȃ�ł��邩�ƕ�����Ă��z���ł��Ȃ��B �G���̌������킩��킯���Ȃ��A����̓����������鎆�����t�ɕ\���̃f�U�C���E���[�N�̈ꕔ�Ƃ��Ă��邩�̂悤�Ɍ����Ă��܂��B �Ȃ����L���Ċm���߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��u�G���\���v�͎G���̃R���Z�v�g�̈ꕔ�ł����Ȃ����A�K���ɃR���Z�v�g��`���悤�Ƃ���A�G�����A���s�ЂȂǂ����o�� ����u�}���v�u�G�������S�v�f�U�C���łł��������Ă���B �i�����̃��[�v���^�f�U�C���j �����̗�O�ƂȂ钆�E���̊��������̕\����A���������g�������ň͂����u�����̃��[�v���^�v�f�U�C���́u�퍑�ʐ^���v1894�ŏI����Ă���悤���B �i���ł��w���u�N�w�v�u�W�]�v�ȂǁA���E���̊��������̕\���̂��̂����邪�A�{���́u�G�������S�v�́A���̎G���̂��߂ɃX�y�V�����Ƀf�U�C�������� �̂ł������B���L���Q�Ɓj �i���h�ȎG�����̃��S�͍ŏ�����j �����A���������̃��C�A�E�g�ł����Ă��A�B�M�Șa�M��y���K�L�ɂɂ��G�����̘a���̂̃��S�A�m���S�V�b�N�̂̎G�����̃��S�𒆐S�ɐ�����f�U�C�������� ���瑽�p���� �Ă���̂́A�����[���B �u���{�n�k�w��v1884�u�����̗F�v1987�ȂǁA�n�b�g�ɃR�[�g�A�a�m�Ƀ`���r�E�q�Q�̂͂˂���������������G�����̃��S���A���������̃��C�A�E �g�ł����� �ɂӂ��킵�����̂ɂ��Ă���B �i�J�^�J�i�G���́H�j �J�^�J�i�G���ł́u�n�}���~�v�������E�j���|��1903�u�J�}�N���v���q�E�C�̉�1909�A�l���̕\���́u�X�R�u���v������G����/��M�F�{���O�� 1916�͂��邪�A�J�^�J�i��薼�Ɏg�����ʔ����ł����āA������J�^�J�i�G���Ƃ͈Ⴄ�ł��낤�B�t�ɂЂ炪�Ȃ́u��ɂĂ肠��v�����E�B���1890 �́H �u�O���q�b�N���|�v1910�A�u�W���p�[���E�}�K�W�[���v1910�u�e�[�u���v�i�����w�l���B�u�K��j1912�A�L�̕\���́u�ƒ�p�b�N�v�i�����y�V�Ёj 1912�́H �u�O���q�b�N���|�v�v�͑唻�G���Ō|�W�A�͎m�A���҂�̎ʐ^�����o�I�ɂ��V�N�ƕ]����Ă���B �u�E�I�[���h�v��������}����1913�A�u���a�`�[�l���v�����E���a�`�[�l�����s��1914�A�u�r�A�g���X�v�����r�A�g���X��/�\���G���R���v 1916�A�u�^���E�̌��ЁE�I�����s�A�v�����I�����s�A��1916�u�J�t�F�E�o�[�v�����E�H���� 1916�A�u�G�t�B�V�G���V�[�v�����G�t�B�V�G���V�[������1917���B�J�^�J�i�G���炵�������߂�̂Ȃ�A�Q�O�N�㒆���ɂȂ낤���H�ʐ^������{�i�I�� �\�ƂȂ�R���[�W�����g���͂��߂���B ���̎���ɂȂ�Ɖ摜���u�C���X�g�v�ƂȂ�A���F����̃��C�A�E�g�ւ̃R�_�����́A���݂Ɠ����ɂȂ�B �i�g���₷�����C�A�E�g�A�}���ƈӖ��j �}���ŃV���v���Ȃ��̂ɁA�~�i���~�j������B �ۂɉ摜�u���m�|���`�G�v�Łu�c�c�����v1877 �ۂɕ����u�����V�����v1867 �ۂɉ摜�u�X�X�L�Ɍ��v�Łu�ނ����́v1901 �ۂɉ摜�u�ΐ��ƎR�v�Ɋw�����A�͂��܂̒j�����͂킹�āu���N�v1903 �ۂɉ摜�u���m�_�b���v�Łu���ƊE�v�\���F�������j1904 �ۂɉ摜�u�M���V���_�b���v�Łu����v���v1904 �~�Ɋe����̒j���C���X�g�ň͂��āu�����v1913 �摜�u�Ԋہv�ɕx�m���͂킹�āu����{�v1914 �ۂɕ����u����v1914 �ۂ��n���ɕ����u�Ԃ��݂��v�����E���{���q��E������1905 �ۂ��n���Łu�H�Ə��L���G���v1905 �Ȃ��Ȃ��A���̃f�U�C���͎g���ɂ����悤���B �i�ӎ��Ɗi���j ��x�̓f�U�C�i�[�Ȃ�g���Ă݂����Ă��A���ۂɎg�������Ȃ�ɂ́u����Ȃ�̈ӎ��v�ƃN���C�A���g�́u�v���v�Ƃ̊i�������肻�������E�E�E �ۂɒ��ԐF�̗ΐF�ŕx�m�R�ɏ��u�s���G���v1323 �\���S�̂𓌗m�n�}�B���S�ɐԊۂɔ������u���F�V���{�v�莚�F���������Y1921�B �ԊۂɁu�x�v1919 �I�����W�ۂɁu�����v1919 �ԊۂɁu�v1915 �Ԋۂ����Ƃ͒������u���m�{�v1927�É��E�������B�� �Ԃƍ��ŃO���O���~�������āu���e���v�\���F���䗺�g1927 �i�m�M�Ƃ̊ہj 30�N��ɂȂ�ƁA�g���ɂ����Ԋۂ��g���̂́u�m�M�Ɓv�ɂȂ��Ă��Ă��� �Ԋۂɐ}�ۂ͋ɓ��n�}�ŁA�l�ވꓯ��`�u����v���������1935 �I�����W�ۂɕ����u���v������R�l��1935 �i�s���̊ہj �ԊۂɁu�V�N���v�Ɠ��ꂽ�u���o�v�i�����j1946 �Ηt�̉~�̒����Ɂu��v�v1946 �~�̐}���̓��C�I���̕�������H�u�w�l�����v1946 ��������̂͒|�v����ŁA�ۂɉ摜�ؔŁ{�����u�Vj�]�_�v1914�ŁA���̊ۂ𗇐g�Ђ��E�������S���グ�Ă���B �n�[�g�ɕ����u���u�v1921������ˁI�I �u�N�Ɠ��{�v1917���A�n���V�������Ă��邼�I �i�摜�Ɠ����j �����ł́u���m�v1891���t���b�N�R�[�g�p�̔n�ɐU���p�̎��B �u�������E�v1906�́u���Ƙa�������v �M���V�����ɓV�n�Ɩq���u�w���v1910 ���Ђ邪�O�H�u��t�v�����E���{���q��t�����Z�E��t��1911 ��ɂ��G�ꂽ�A�L�̕\���́u�ƒ�p�b�N�v�i�����y�V�Ёj 1912 �u�e�[�u���v�i�����w�l���B�u�K��j1912�͒r�̌�̃A�b�v�B �r�Q���Łu���E�v1913 �M���V�����ɓV�n�u�䓙�v1919 �J���X�H�H�����ԊۂɁu�x�v1919 �V�n�u����v1920 ���Ǝq���C���u���w�Z�Ɖƒ�v1926 �������̏ۂ̎ʐ^�Łu������v1926 ���n�G���́u�n�v���g�� �uHorse�@Journal�v1925 �u���n�t�@���v1926 �R�n�́A�܂�������������ł���悤���B �i�V�n�E�h�E�p�k�j �ԊۂɓV�n�u�s�i�v�����N�c�s�i�c1924 �ԉ~�ɔn�Łu�����v�얞�B�S�������o�ϒ�����1928 �ԊۂɓV�n�u�N�P���v�鍑�N�P���1926 �h�����邼 �u���̎���v1925 ���C�I�����o�Ă����B �u���ێЉ�^�C���X�v�u�֓��v1925�u�����`�_�v1925 �摜�͂Ȃ����A�G��������z�̓����u��Q�v�v�v�ԉ��h�~�c1925 �������Q���H�u�_���w�G���v1926 �h�����e�������āu�h�C�c���_�v1941 �p�k�ł��낤�u�嗤�v1938�B��[���q�̃f�U�C���́A�������p�k�����点�A�㕔�ɐ����������炤�B �i�C���X�g�j �ѓc���̃g�b�p���i����j�����فH�Łu�L���O�v���u����i���N����j�v�H�����ꂩ�̌R�͂̃C���X�g���������A���炵���ł�������ł������B�s�N���Ő\�� �킯�Ȃ��̂����A�R�͂����̃C���X�g�ł���u�L���O�v�ŁA���̌R�͂̐������Ԃ��r�͂����Ă���u����i���N����j�v�Ȃ̂����A�L��������Ă���B �i���r�t���Ƌ������j �G���̓ǂ݂₷�������߂�̂͊����ł���B�������A�ѓc���̃g�b�p���i����j�����فH�ŁA�����K�����Ȃ������Ȏg���Ƃ��������̈������A�����ɓǂ݂₷�� ���Ă����O�̑����G�������邱�Ƃ��ł���B���M�̗͊����x�[�X�ɂ����������̃t�H���g�͓ǂ݂₷���A�U���Ă��郋�r�܂Ŏ����̗����W���Ȃ��B |
| �y��
���͂킵���Ⴂ�z����҃T���}���� �A�C�[���K���h��p�Ђɂ����̐l �E�E�E�����g�����Ƃ����̂͂Ƃ����͖̂{���U���łȁA��Í�����ɓG��������G���g�̂܂������̂ɂ�����B�I�[�N���G�� �t�̂܂����ł���̂Ɠ������Ƃ�B�킵��̓g������苭���B�킵��͑�n�̍��łł��Ă���B �킵��͊�ł��낤�Ɩ̍��̂���悤�Ɉ������Ƃ��ł���B�g�������͑����B�����Ƒ� �����A�킵��̐S�������N����I�����킵�炪��|����Ȃ���A���邢�͗d�p�̉ő� ���łڂ��ꂽ�萁�������邱�Ƃ��Ȃ���A�킵��̓A�C�[���K���h�����������Ɉ����A ���̕ǂ��ӂ��č����ɕς��邱�Ƃ��ł���̂�B�v �u�����ǁA�T���}���͂����͂����܂��Ƃ���ł��傤�ˁH�v �u�ӂށA�����A���悤�A�������邶��낤��B���̂��Ƃ͖Y��Ƃ��B���̂Ƃ���A���̂��Ƃ� ���Ē������ƍl���ʂ����B�����A�悢���ȁA�G���g�����̑����͂킵���Ⴂ�B�̖��ɂ��� ������Ⴂ�̂���B ���̂���炪����݂�ȕ��N���Ă��܂����B�����̐S�݂͂ȓ�������� ���A�A�C�[���K���h�̔j��Ƃ������ƂɌ������Ă���B���������͊Ԃ��Ȃ�������x�l���n �߂邶��낤�B�����炩�C���������܂낤�B �[�ׂ̈��������ލ��ɂ͂ȁB���������݂�ȍA������ ���Ƃ���낤�āI�����A���͂����͉̂��i�R�����悤�I�s�����͂܂��܂������B�l�� �鎞�������B�������ē����o���������ł������������̂�B�v ��颂͕��������܂��Â��B�݂�Ȃƈꏏ�ɂȂ������炭�̂������Ȃ���B�������ꎞ�̌�A ����̐��͎���ɂ������șꂫ�ƂȂ�A���ɂ͂ӂ����Җق肱��ł��܂��܂����B�s�s���͂� ��̔N�V�����z��ᰂ����A�ӂ����Ԃ��ł���̂����܂����B�Ƃ��Ƃ����܂��ɂ��ꂪ�ʂ��グ ��ƁA�s�s���͂��̖ڂɔ߂����ȐF�������Ԃ̂����邱�Ƃ��ł��܂����B����͔߂������ł͂� ��܂������A�s�d���킹�����ł͂���܂���ł����B�o�̖ڂɂ͌�������܂����B�܂�ł���� �v�l�̈Â���˂̉��[���̉�������ł��邩�̂悤�ł����B �u�킪�F��A���_�傢�ɂ��蓾�邱�Ƃ�B�v����͂�����肢���܂����B�u���킵��́A�j�łɌ� �����Đi�݂��邩�������B����͑傢�ɂ��蓾�邱�Ƃ�B�G���g�Ō�̐i�R��ȁB������ �Ƃ����ĂЂ����������܂܉��������ɂ���A�j�ł̂ق����A�x���ꑁ����킵���������� ���B���̍l���͂��������ƑO����킵��̐S�Ɉ���Ă��Ă������B�����炱���킵��͍������� �Đi�R���Ă���̂�B�Ȃɂ����ɂȂ��Ă���ĂČ��ӂ����킯�ł͂Ȃ��B�Ƃ���ł��߂ăG���g �Ō�̍s�i�����ł��̂ɍ��l�ł������邩������ʁB�����|�B�v����͒Q�����Ă����܂����B �u�킵��͂��̐�������O�ɑ��̐l�����������Ă������邩������ʁB����ɂ��Ă��A�킵�� �̂̒��ɉ̂���G���g�������Ƃ̂��Ƃ��{���ɂȂ�̂������������̂��B�t�B���u���V���ɂ� ����x�ɉ���������̂��B�����A�킪�F��A�̂Ƃ������͖̂Ɠ����ŁA���ꂼ��̎����� ���Ă͂��߂āA���ꂼ��̎d���Ŏ���������́B���ɂ͎��@�ʂ܂܂Ɍ͎����邱�Ƃ�����B�v �G���g�����͔��ȑ����łǂ�ǂ�����čs���܂����B |
| �@�₽���r��n�� �킵��̎�����݁A �����������B ��ƍ��I�� �Â����̂悤�� �����C�Ȃ�����B �����ǒr�Ɨ���́A �����Ă��������B ���ɂ����C������B ���̏�ق������̂́]�] �u�ق��A�ق��I�킵��̂ق������͉̂�����H�v �������Ȃ��ŁA�����Ă��āA ����ł�悤�ɁA�₽���āA �A���킩�ʂɁA����ł���B �Z���ĂĂ��A��������ʁB �������Ƃ���œM��A �����R�Ǝv���A ��𐁂��グ�Ǝv���A ���炩�ŁA���ꂢ�Ȃ��́A �����ɉ����A���ꂵ���ˁB �킵��̂ق����̂́A������A �`�C�����Ղ�� �\������ |
|
�@
������ɔ҂��Ă͂Ȃ�Ȃ�
�P�[�e�E�R�����b�c�ɂ��� �ޏ��̏����̔ʼn�V���[�Y�ł���u�D�H�v�̓h�C�c�ł̗��j�I�ȘJ���҂̖I�N�ł����B���̗��j�I�������R�����b�c�͔ʼn�Ƃ�����Ƃł����B�x�������ł̓��E�w�l�̔ߎS�ȏ�i�����|�X�^�[��}�w���҂̈ÎE�������d�������Ă��܂��B1933�N�A�q�g���[�̎A�C�A�i�`�X�̈�}�ƍّ̐��m���ɂ��A���۔��p����ёO�q�|�p�����ĕ\���́A�u�ޔp�|�p�v�Ƃ���A�����ق���ߏo����A �P�[�e���g�����E��ǂ��A��i�̓W�����ւ����܂����B ��ꎟ���E���ő��q�y�[�^�[���n�Ŏ����A����E���ł͑���D��ꂽ�R�����B�b�c�́A�I�풼�O��1945�N4���Ɏ��ɂ܂��B �P�[�e�E�R�����b�c�̓W����ł́A���̃t�@�V�Y���Ɛ푈�̎���ɁA�����E���\���ւ���ꂽ�|�p�Ƃ��`���A�˂�u���̃V���[�Y�v�������܂��B ���́A�e�R�����B�b�c�W�h���J�Â��ꂽ���c�s���ʼn���p�ق�����Ă��܂��B ���n�Ɉ�����ꂽ�u���̒��̎��v�A�ˑR�݂͂�����u���v�Ȃǂł��B�e���ƔN��A���a����d�ˍ��킹����i�������܂��B�Ȃɂ��ł��Ȃ��V�k�ɋ�����t�@�V�Y�����A�ޏ��̌��ɂ��݂����낤�Ƃ��Ă��܂��B 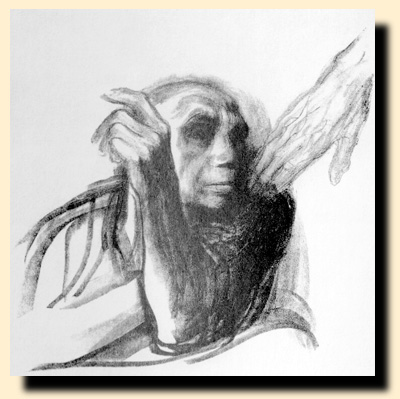 �����N�̐��E�勰�Q�������O�O�N�i�`�X�ƍق��������邱��A�P�[�e�̐����͂ǂ�Ȃӂ��ł������̂��낤�B�V���y���O���[���u�w�l�͓����ł��Ȃ��� �Έ��l�ł��Ȃ��A�����ꂽ��̂݁v�Ƃ����W������������A�ꂽ��h�C�c�̋ΘJ�����̐����ꓬ�̒��S����̕`����ł������P�[�e�E�R�����B�b�c�́A�ǂ�ȐS ���ŁA���̐N���R�l�Ƃ��Đ��Y�҂Ƃ��Ă����ꐫ��F�߂��V���y���O���[�̍��߂����������낤���B���̍�������{���͂��N���푈��i�s�����Ă��ăi�`�X���q�Ɋׂ� ���B�P�[�e�̐��͎������ɓ͂��Ȃ��B �u�P�[�e�E�R�����B�b�c�̉�Ɓv�ɋ{�{�S���q�͏����Ă��܂��B �k���l��N�O���B���l�Z�N�Z����l ���̕��͂ɂ�[�NjL]�������� ���܁Z�N�A�V�C�o�Y���ɂ���āA�u�P�[�e�E�R�����B�b�c�\�\���̎���A�l�A�|�p�v�Ƃ����{������킳�ꂽ�B �@���O�O�N�A�i�`�X���������Ƃ��Ă�������ʂ��āA�P�[�e�͂ǂ����Ă������낤�Ƃ����킽�������̒m�肽���_���A�V�C���ɂ���Č���Ă���B ����ɂ��ƁA�P�[�e�E�R�����B�b�c�͈��O�ܔN�A�i�`�X�ւ̓��}�������߂ɁA�q�g���[���{�����ƂƂ��Đ��삷�邱�Ƃ��ւ���ꂽ�B�����P�[�e�� �Z�\���ɂȂ��Ă����B�ޏ����琧��Ɛ����Ƃ�D�����i�`�X�E�h�C�c���������~�������͈̂��l�ܔN�܌��ł���A�P�[�e�́A�l�ގj���L�O���邱�̃i�`�X�� ��̓���ڌ����Ă�����߂̈��l�ܔN�����ɁA�h���X�f���Ŏ��\���̐��U���I�����B �@�i�`�X�̔��Q�̂����ɂ��������ӔN�̏\�N�Ԃ��A�P�[�e�ɂƂ��Ăǂ̂悤�Ȏ��X���X�ł��������Ƃ������Ƃ́A���悻�z�������B����ł��ޏ��͂������� ���A��������Ɩڂ������ċ��낵���V��̊��߂��ق��肽���������Ƃ������B�i�`�X�̍~�������N�̌܌��A�P�[�e�́A�ǂ�Ȏv���ɂ����āA�h���X�f���̐V�� ���߂����낤�B �Ƃ��Ă��܂��B �������A�{�{�Ɠ����悤�Ƀt�@�V�Y�����ɂ������R���r�b�c�̐��́A�`����Ă��܂��B���̈Â�����́u���̃��b�Z�[�W�v�̑����� �R���r�b�c�́A�Ƃ�ł��Ȃ��V�k�̑N���Ȏ��ȉ���̊j�S�����ݍ���ł��܂����B �������͔��p�ق̕������Ȃ���A�p���Ȃ���A�Â��C�����̎�����Ă��t�������Ȃ�����A���c�s���ʼn���p�ق̍Ō�̓W���ƂȂ� �ꖇ�̔ʼn�̊�Ղƕ����̊m�M������������ċ��L���܂��B���̃R�����B�b�c�́u�⌾�v�łƂȂ�����i�s�u��ɔ҂��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�t���A����Ɍ������������ՓI�ȃ��b�Z�[�W�������Ă��邱�Ƃ�����I ���łɗ�V�V�ɂȂ�E�E�E�M��܂��A���\�̋@���D���Ă��A�N���Ȉӎu������I �����r�̉��Ɏq�ǂ���������������ƕ�������Ŏ���Ă���B  �s�u��ɔ҂��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�t 1941�N���@ ���g�O���t�i�]�ʁj �P�[�e�͑����̃��b�^�Ɏ��̂悤�Ȍ��t���c�����Ƃ����B�u������̗��z�����܂�邾�낤�B�����Ă�����푈�͂����܂��ɂȂ邾�낤�B�@�\�@���̊m�M ���������Ď��͎��ʁB���̂��߂ɐl�͔��ȓw�͂�˂Ȃ�Ȃ����A�������A���Ȃ炸�ړI�͒B�����邾�낤�B���a��`������Ȃ锽��ƍl���Ă͂Ȃ�� ���B����͈�̐V�������z�A�l�ނE�Ƃ��Ă݂�v�z�Ȃ̂��B�v |
| |
 �g�b�v�y�[�W�ւ��ǂ�
�g�b�v�y�[�W�ւ��ǂ�